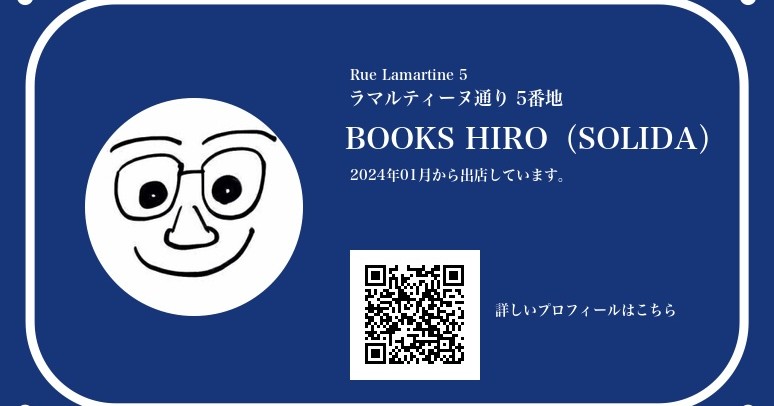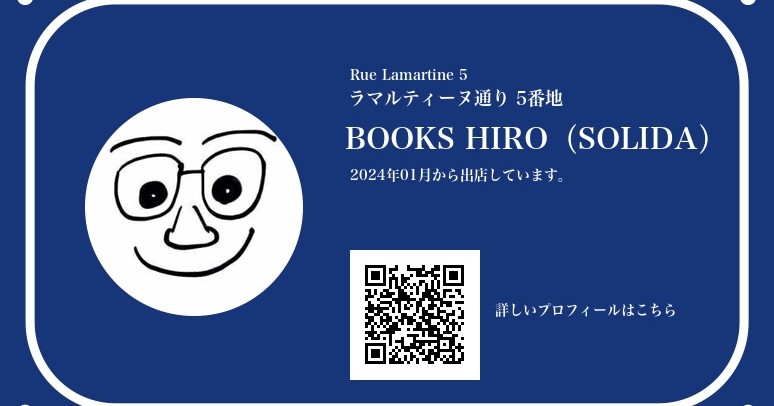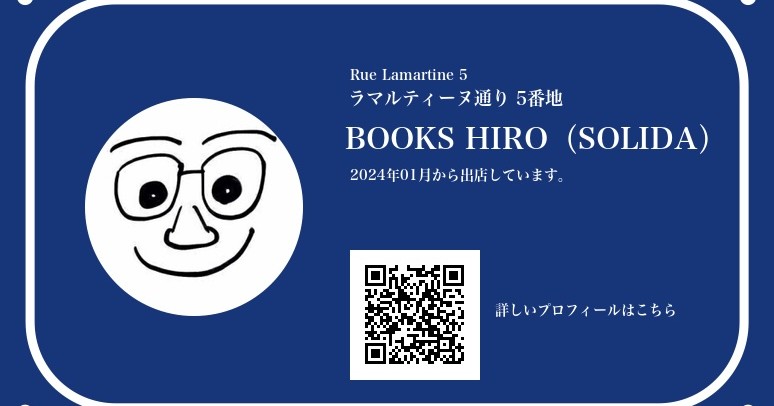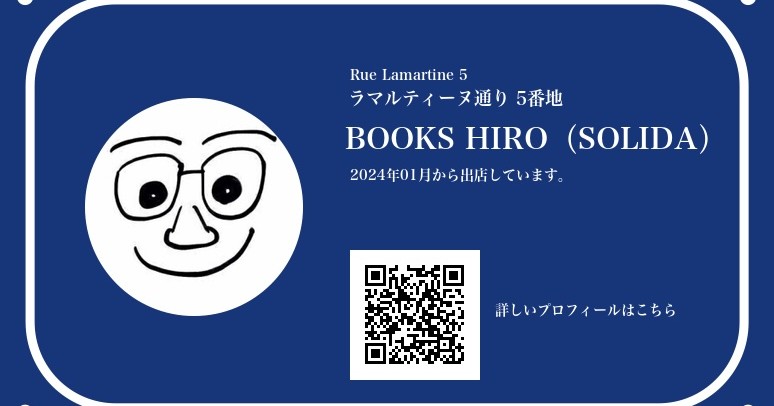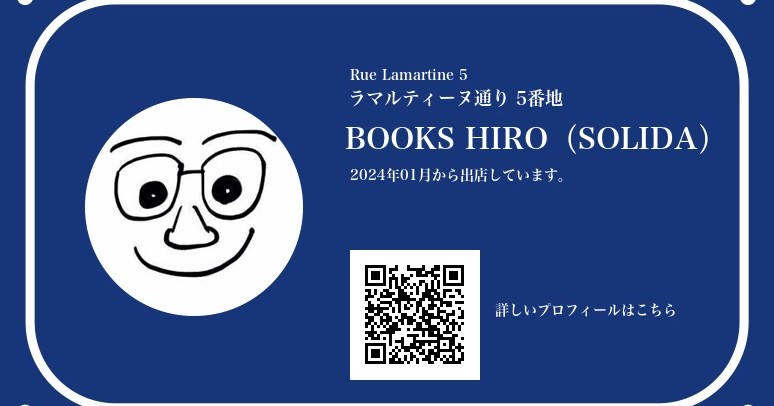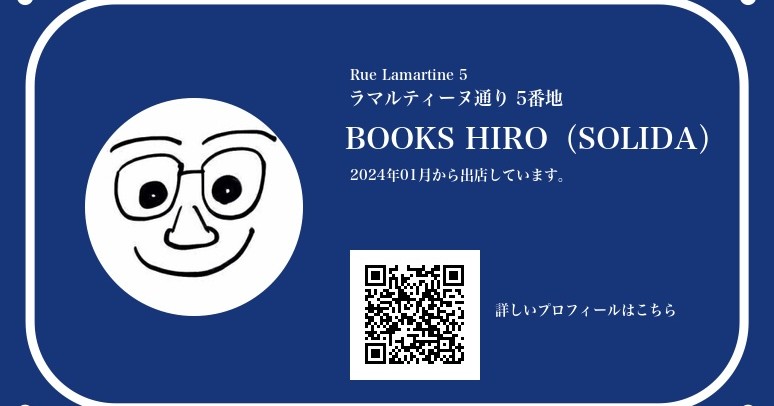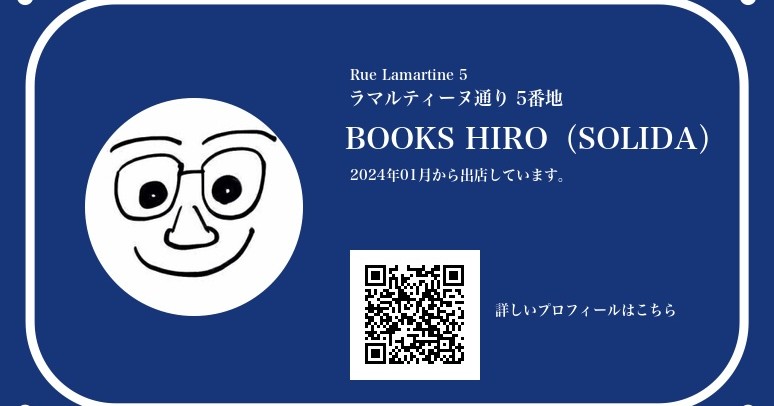BOOKS HIRO通信 第157号
(1)みなさまこんにちは
『菊池寛アンド ・カンパニー』(鹿島茂著 文藝春秋)を岸リューリさんの書棚(RIVE GAUCHE店)から購入しました。6月の発売当時から欲しかったのですがなぜかためらって購入できず、最終的に購入の後押しをしてくれたのは、表紙カバー裏の惹句の一部でした。
「菊池寛が編集後記を「双方向メディア」として使っているばかりか、予約購読料を1種のクラウドファンディングと見なしていた」
これを読んで、「文藝春秋」という古くからある雑誌がそんな新しいコンセプトで作られたのかという興味が湧いたのです。
70年以上前から、実家では「文藝春秋」を定期購読しており、メインの記事だけでなく、巻末の「社中日記」や読者の投書欄も愛読していたような記憶があります。当然その頃は菊池寛は亡くなっていますし、子どもだった私にはその編集術や革新的なアイディアなどは理解できていませんでした。しかしこの雑誌はとにかく読むと面白かったのです。グラビアや広告も巻頭の有名人たちによる随筆も魅力的でした。
今に至るまで、菊池寛の作品は、『恩讐の彼方に』を除くとほとんど読んでいなかったし、文学的才能と経営の才能を兼ね備えた、稀代の人物であると言う認識もありませんでした。さすがに菊池寛が「文藝春秋」を立ち上げたことだけは知識として知るようになっていました。『菊池寛アンド ・カンパニー』と言う書名も、単に面白い命名と思って買いました。しかし、18ページを見ると、「菊池寛と寄稿者・文学仲間たち」と「菊池寛と、社員や出資者・読者と言う共同経営者」と言う2重の意味があるようです。少なくとも菊池寛自身は同時代の中産ブルジョワ階級の人々のリベラルな考え方に合わせて雑誌を作っていると認識していたでしょうし、それが故にこの雑誌はよく売れたのでしょう。鹿島茂さんがプロデュースしているPASSAGE by ALL REVIEWSの各共同書店にPASSAGE・SOLIDA(実はSOLIDARITY) ・RIVE GAUCHEなどと言うネーミングをするセンスに通じていると一人合点しています。
この本の読みどころはたくさんあります。私がつけた付箋は35枚あります。その大部分の箇所が「生活第一、芸術第二」という菊池寛の方針、そしてその方針での最高傑作は「文藝春秋」と言う総合雑誌そのものであることを示しています。菊池寛の雑誌経営のコツは、彼が自ら革新的なアイディアを出し、実現に至る青写真を全て頭に入れながら、社員に実行させたことでした。その際には、大胆にイノベーションを進め、失敗を恐れませんでした。
大学生になって、思想に目覚めた頃も、この雑誌は右なのか左なのかわからないおかしな存在だなと不思議に思いながら読んでいました。当時の学生運動の嵐の中では、この雑誌は微温的か、または保守反動かとも思ったりしました。でも、とにかく自宅に配送されねれば、なぜか読まずにはいられなかったのです。その理由が、この『菊池寛アンド ・カンパニー』を読むと、わかりました。この雑誌は、上から読者に与えられる雑誌ではなく、編集者と執筆者、読者一緒になって(カンパニー)、不偏不党な議論を楽しむ雑誌だったのです。カバーの惹句の言う「100年前のネットメディア」であっただけでなく、今後100年のネット(と言わないかもしれませんが)メディアのお手本になる媒体であったのです。
なお、この本は菊池寛という傑物人間そのものについても詳しく述べています。なかでも印象にのこったのは、彼にとってはじめての通俗小説、『真珠夫人』に対する高い評価です。菊池寛のバルザック譲りの女性研究のたまものとされていますが、私は今回始めて読みました。男性の書いたフェミニズム小説のうちでは最高傑作と思います。
(2)現在の私の棚主ページです
SOLIDA
RIVE GAUCHE
***
また来週。
すでに登録済みの方は こちら