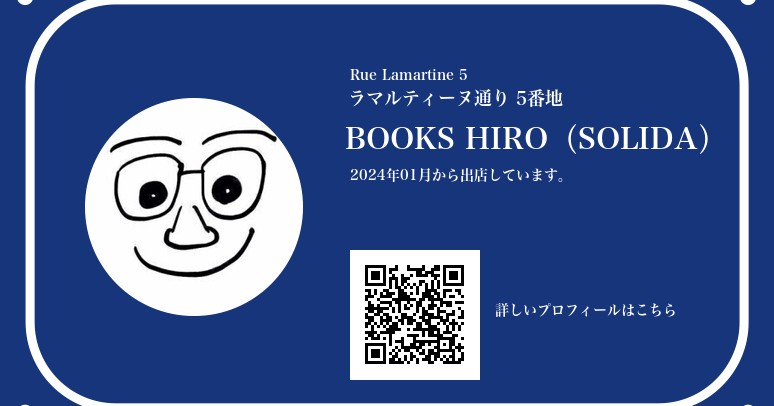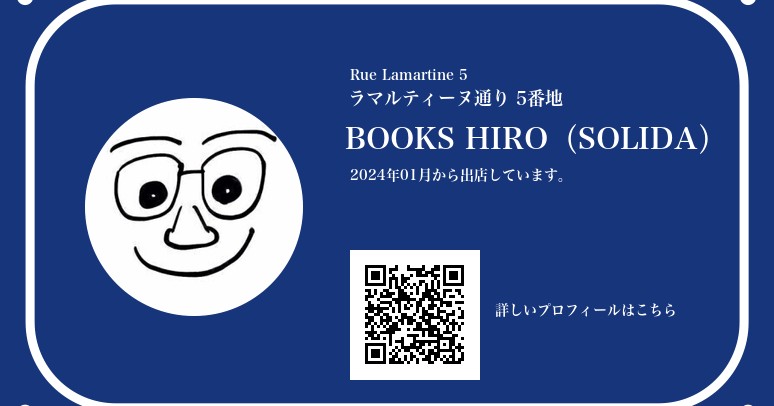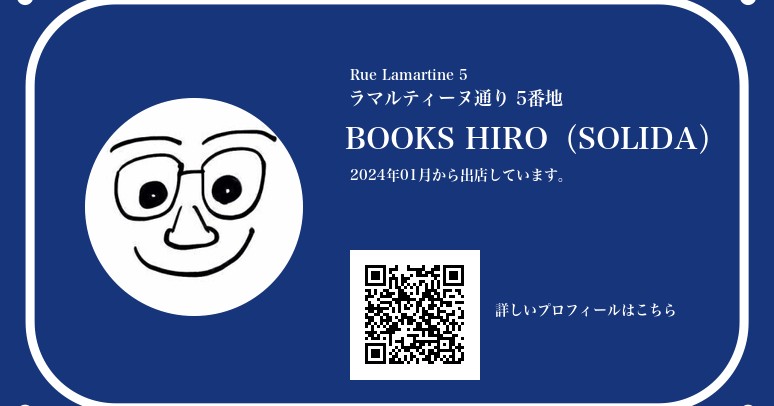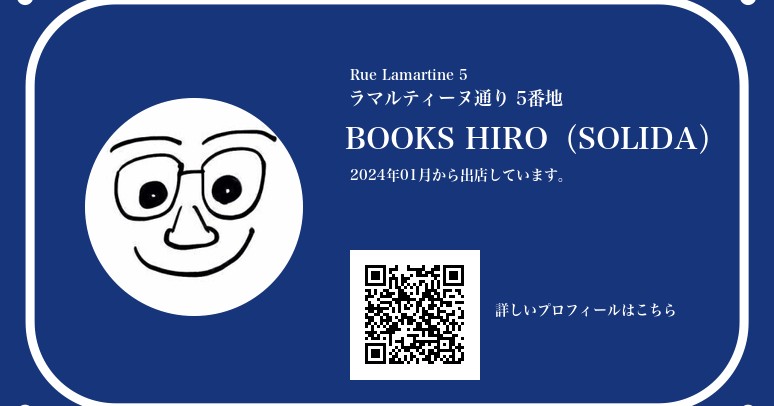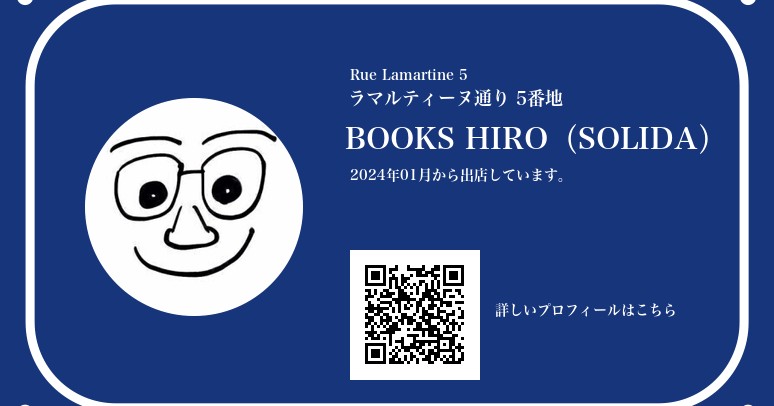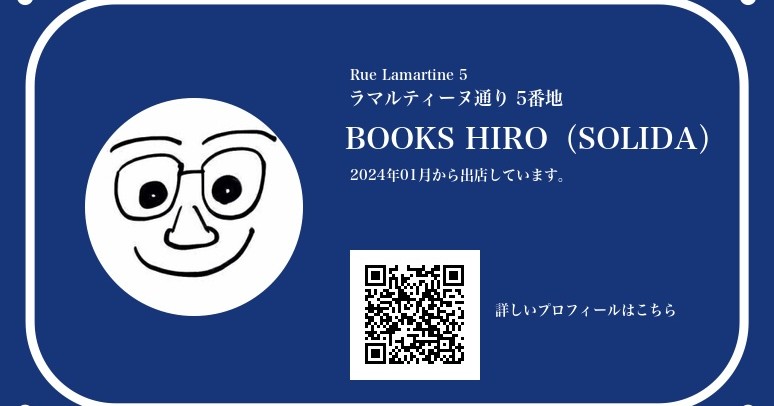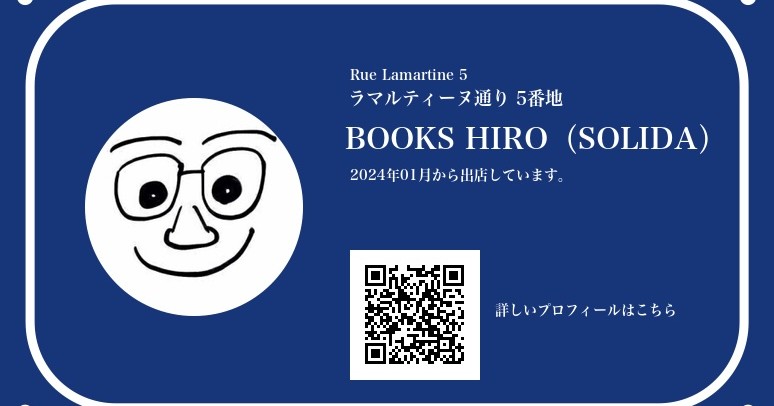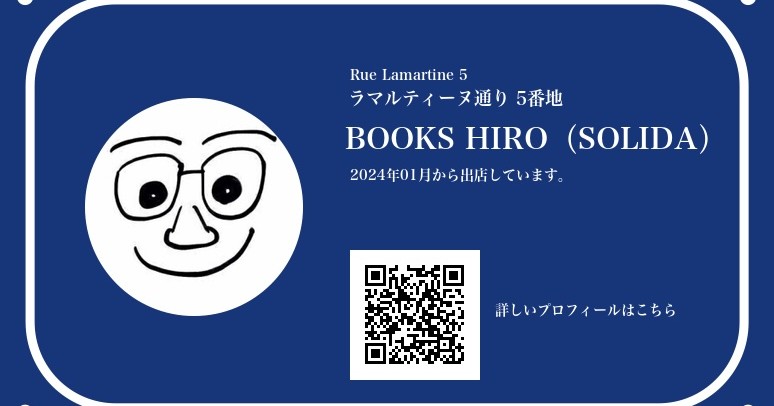BOOKS HIRO通信164号
(1)みなさまこんばんは
RIVE GAUCHEの書棚、「A la ligne」さんから『中世ラテン語の辞書を編む 100年かけてやる仕事 (角川ソフィア文庫)』を購入してすぐに読みました。
(この棚からは以前、『ロシア語だけの青春』を買って読みました。この本もとても面白かったことを覚えています。)
毎日新聞の欧州総局(ロンドン)長(その後論説委員)だった著者小倉孝保がその記者魂を発揮して、自分にとって興味深いテーマを追求した経験から生まれた本です。費用対効果のみを追求するビジネスの多い現在の世の中で、100年を超す時間をかけて、まったく儲からないにもかかわらず、「中世ラテン語辞書」を多くのボランティアの手も借りながら作りあげた人々の物語です。
一般の人が多いボランティアは、ワードハンターつまり単語とその用例を各所の図書館を回って古文書から収集する役割を果たします。集めたデータを使って、ある一つの単語の語義と用例を完全に記述するには、数ヶ月かかることもあるそうです。このような仕事は義務感だけでは達成できず、辞書つくりという仕事を愛し、楽しみながらやることに自然となるそうです。
新聞記者である著者は、自分の仕事と「中世ラテン語プロジェクト」の仕事を比較してこう書いています。
「彼らは時間に縛られず、とことん原典にあたる作業を自らに課していた。事実上、締め切りのない現場だった。スピードよりも正確性を重視していた。古い文献から立ち上がってくる過去の人々の声と対話しながら、それを後世に伝える作業を続けていた。僕たちの仕事が鮮魚にこだわる水産業だとすると、中世ラテン語辞書プロジェクトは過去の遺産を守って木を植え、未来のために山をつくる林業だった。緑豊かな山は新鮮な空気をつくり、見る人に精神的な安らぎを与える。」
著者は新聞記者らしく足を使って、すでに終了したプロジェクトにかかわった人々を探し当て、直接話しを聞いて回ります。こうしないと、プロジェクトの仕事ぶりは忘れ去られてしまうでしょう。この結果、言葉とそれを基礎とする文化を守ろうとする貴重な努力が、爽やかな調子で描かれています。
隠居めいた自分の暮らしを考え直し、「好きなテーマ」の追求とその文章化を更におし進める気に、ならせてくれましたが、その意味で非常にありがたい本です。
なお、ラテン語関連では同じRIVE GAUCHEのAsinus Booksさんの書棚に『羅和辞典 改訂版 LEXICON LATINO-JAPONICUM Editio Emendata』や『ラテン語名句小辞典』があります。近所の書棚なので両方ご覧ください。
(2)現在の私の棚主ページです
***
また来週。
すでに登録済みの方は こちら