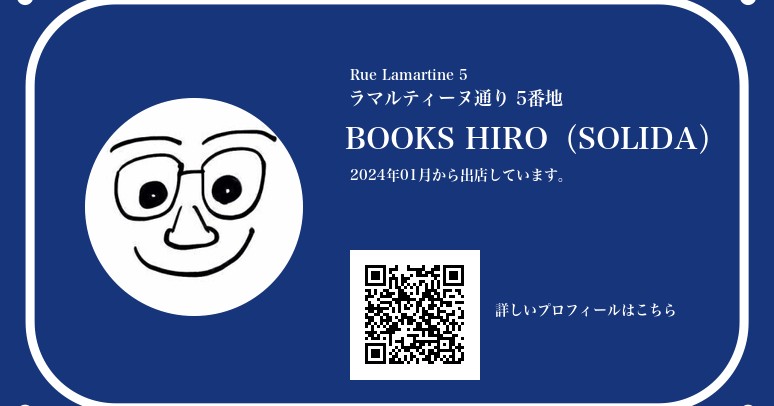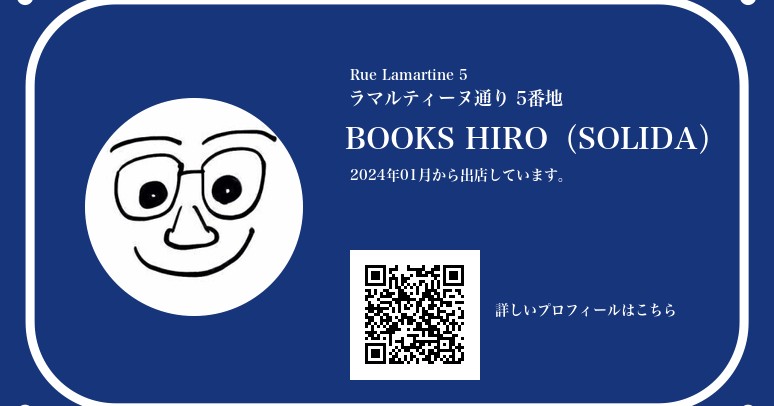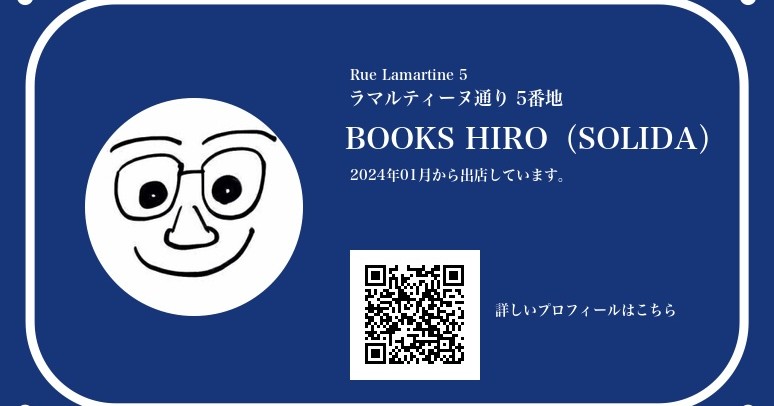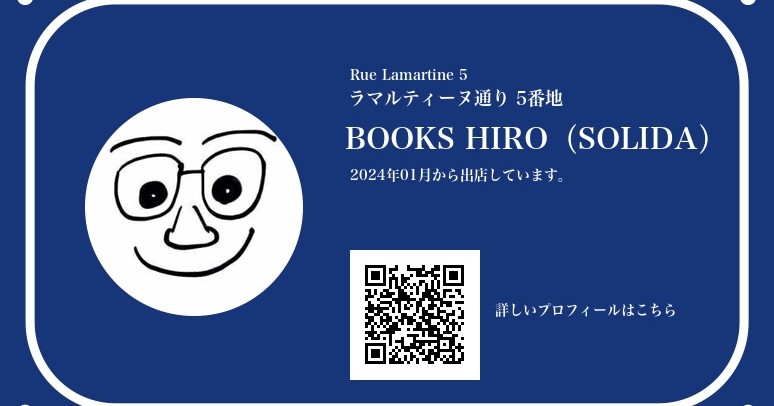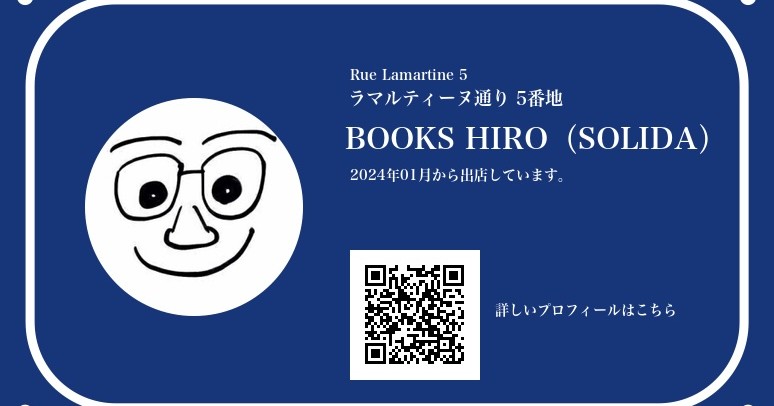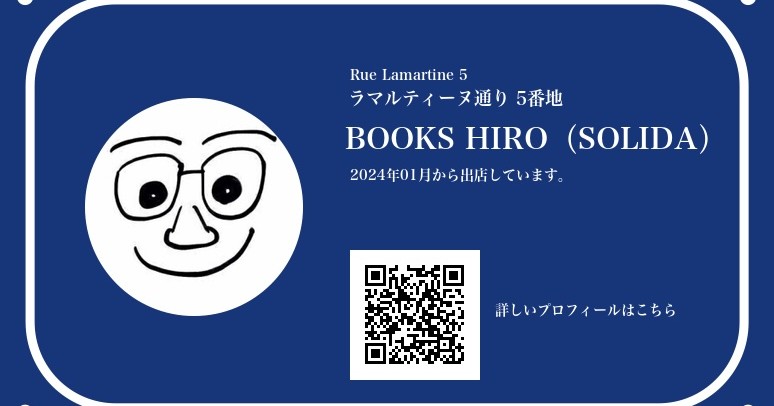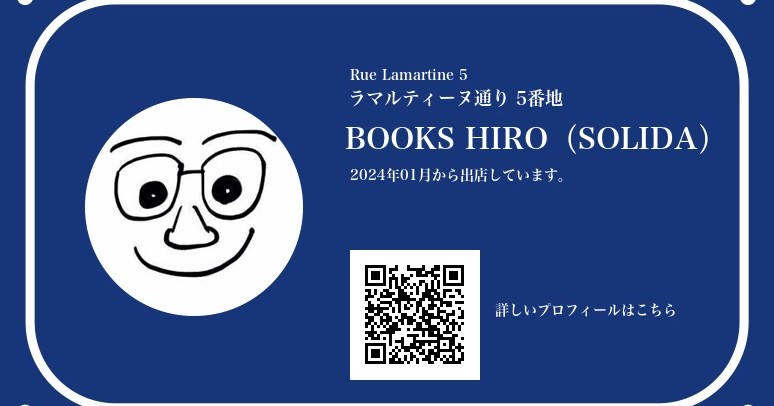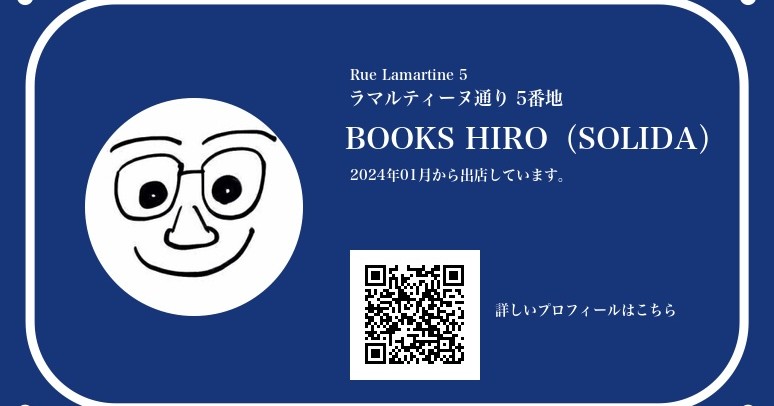BOOKS HIRO通信 第166号
(1)みなさまこんにちは
『闊歩する漱石』(丸谷才一 講談社 2000年)を楽しんで読んだ。
丸谷才一はこの評論集で、漱石の『坊っちゃん』、『三四郎』、『我輩は猫である』を論じている。丸谷才一がこの三作品を選んだことに共感した。私の好みと一致している。それは何故なのか、を考えることがこの本を読む強力なドライブとなった。
まず、取り上げられるのが『坊っちゃん』。その主人公の粗野とも思えるほどのあかるい饒舌・啖呵。登場人物はほとんどあだ名で呼ばれる。主人公の名前も明かされない。ここがユニーク。祝祭的な面白さだという。ラブレーなど西欧古典の語り口に似ている。私はこの豊穣な表現は開高健の作品にも通じていると感じた。読んでいて快感を覚える。
次に、『三四郎』の書き出し(上京する三四郎が列車内で体験することの描写)部分のうまさと、偶然同席した広田先生の持つ世界への視点を書いた漱石のグローバル性が秀逸。その割に日本内に縮こまる三四郎を描く後半の記述が意味深い。丸谷才一は書いていないが、先輩の理学士野々宮さんは実は世界に通じる研究をしているし、広田先生の教養は日本に閉じこもってはいない。ただし、ふたりとも日本社会の人々一般に対する働きかけはしていない(少なくとも作品に書かれていない。)当時の日本社会の閉塞性の根強さを描いているのだろう。
三番目の作品『吾輩は猫である』。なんと無名の猫の視点で描かれている。猫は当時の知識人や市井の人々の、一見明るいが実は発展性のない社会を遠慮なく語る。猫の視点であるというのは、素晴らしい工夫で、大人も子どももそれなりに楽しみながら社会のことを考えられるすごい作品である。
丸谷才一は自身の豊富な読書経験をもとにして、漱石のこれら作品の大きな価値と、漱石のその後の執筆活動のもの足りなさを的確に考察し、上手に指摘している。
私の尻馬的感想を書いてみる。漱石はこの三作品の延長路線で書き続ければ、世界的な大作家になるのは間違いなかっただろう。ノーベル賞受賞(とその辞退!)も夢ではなかったろう。それを可能とさせなかったいくつかの理由が漱石または漱石がとらわれていた日本社会にあったのだろう。健康上の理由も大きかった。今後、このことを頭におきながら漱石を読み直したい。読み通していない『文學論』も含めて。現代の作家(例えば村上春樹)との共通点と違いも考えながら。
この本の末尾で丸谷才一は次のように書いている。
漱石はその種の冒険を、あんなに早い時期に、西方の文学者や画家に先んじて、きれいにやつてのけた。すばらしい意欲であり、すごい才能である。文学的環境がもうすこし違つてゐれば、この線をもつと押し進める可能性は十分にあったのに。
ところで和田誠(装幀・挿画)の表紙絵は素敵すぎる。裏表紙の絵も必見。この絵を見ると本の内容を自然におしはかることができる。装幀の極致とも言える。
***
この本(単行本)は昨年鹿島茂さんがSOLIDAの書棚に入荷されたが、すぐに売れてしまいました。とても良い本なので私も(もう一冊入手して)棚に入れようかと前向きに思案中です。
(2)現在の私の棚主ページです
SOLIDA
RIVE GAUCHE
***
また来週。
すでに登録済みの方は こちら