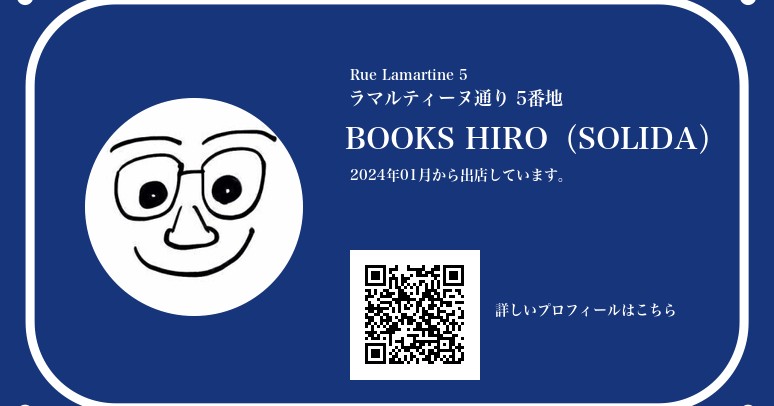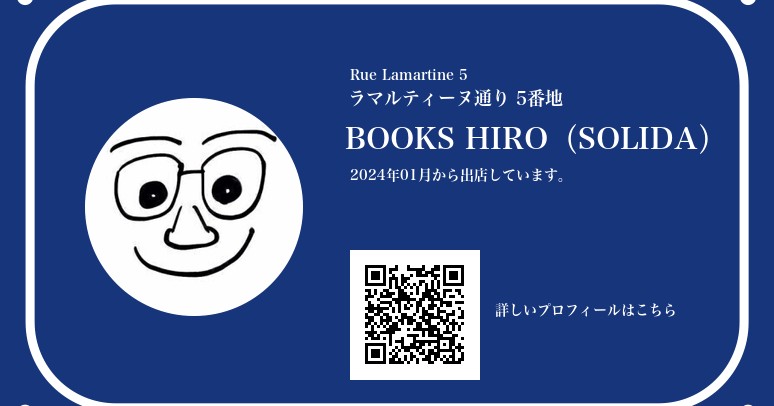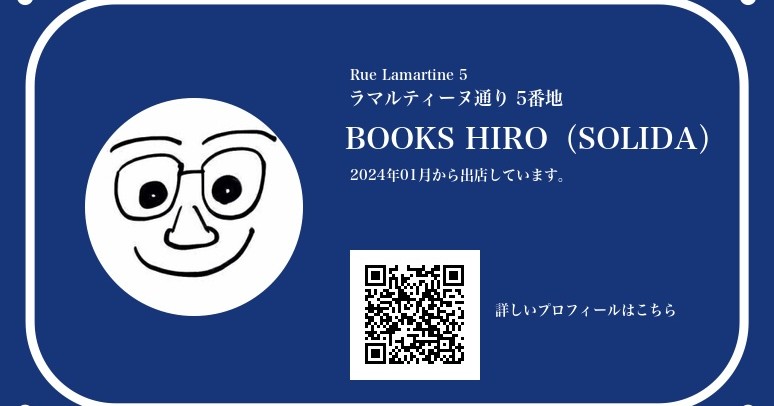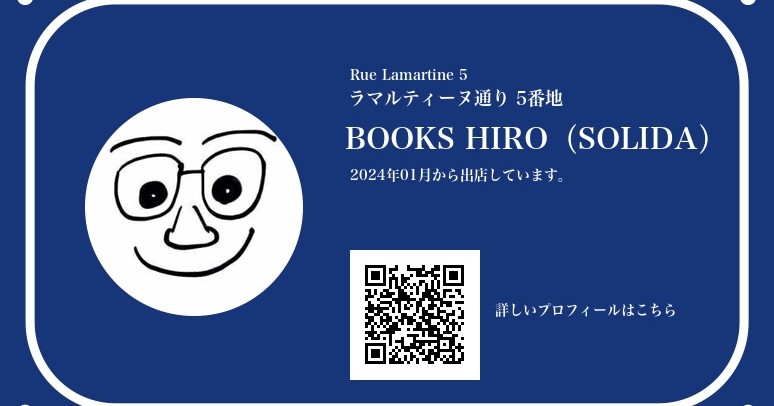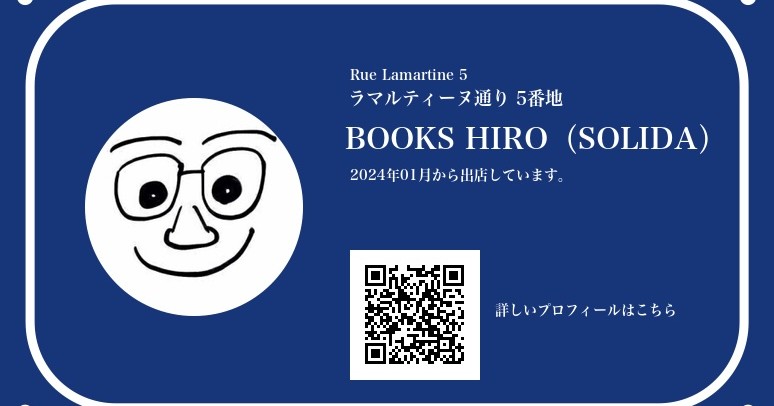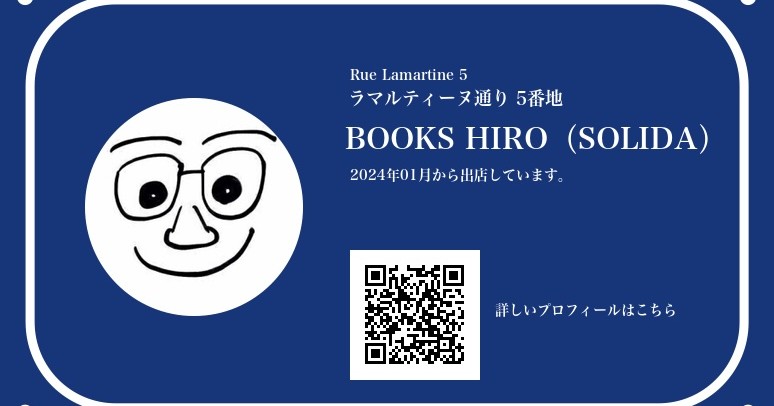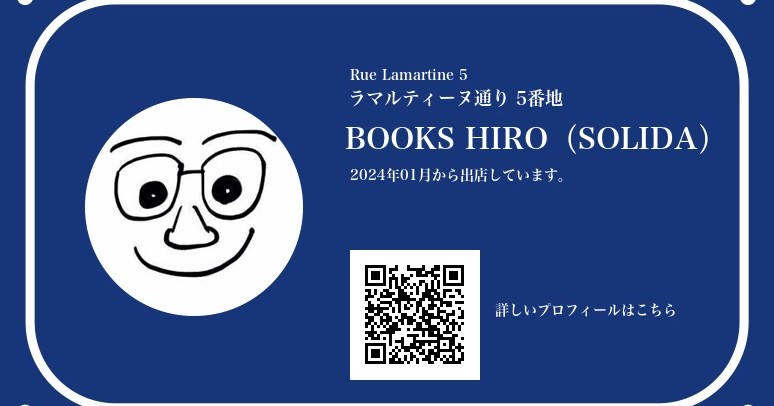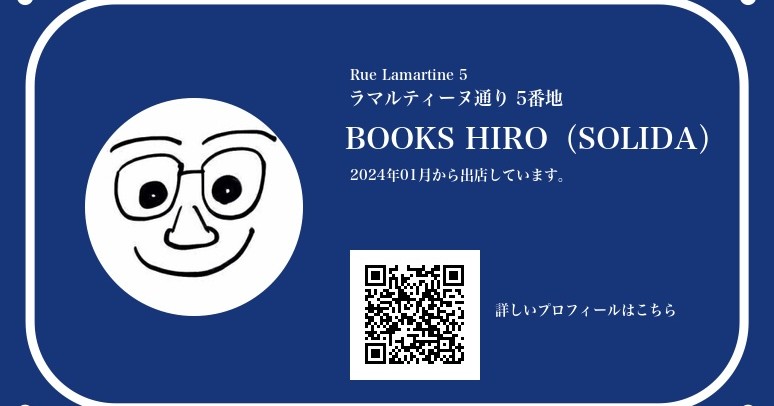BOOKS HIRO通信 第167号
(1)みなさまこんにちは
松岡正剛『世界のほうがおもしろすぎた ゴースト・イン・ザ・ブックス』(晶文社)を読んだ。著者生前のインタビューをまとめたものが本書。読みながら、共感したところにポストイットで印をつけた。
その箇所を以下に一部引用しながら、それぞれに感想メモを書きつけてみる。
こういう生命の全歴史があった上で、やっと自分と言うものがあるわけです。だとすると、自己同一性なんて追求したところで、まったくちっぽけなことだし、たいしたことじゃないと思うんですね。
世の中のすべての知識を追求してみたくなる。いわばゲーテの描くファウストの登場時の心境か。
夜中の三時前には寝ないと決めて、頑なに守っていましたね。なぜかというと、疲れてきたり弱ってきたりしてからが編集の勝負なんですよ。
毎日これをやるには体力がいる、しかしその見返りとして大きな成果(知識)が手に入る。あこがれるが、体力のない私には無理でした。
(部分において全体を構想する)拠点のほうは、私のばあいは好みも手伝って、天文学や物理学から探り始めている。とりわけ素粒子論には格別の可能性を感じて、ハイゼンベルクの原物質仮説や、発表されてまもないホヤホヤの湯川秀樹の素領域仮説をむさぼっていた。(中略)いったんマルクス学の筋を「物質の現象学」に限定してのみ扱おうと考えていた。
広範な知識を得ようとすると、当然のこと。理系の知識を持ったひとはなんでも「掘り下げて」考えたくなるのだと思う。素粒子のことを知っているからか。
そもそも読書と言うのはどういう風に起こっているかという事は、外から観察してもわからないんですよ。本と頭の間で起こっていることが外に伝わってこない。編集学校ではそれを取り出せるように工夫したんですが、(大学の)限られた授業時間の中で、しかもあの大学の教室と言う単位の中ではそういうことを起こす事は難しいなと思いました。僕の考える読書スキルからすると、その程度では何にもならないんです。三○冊位を並行読みしないとわからないことがあるということを体感してもらいたいわけで、そういう事は無理だなと思いましたね。
確かに限られた時間でできることではない。無限に近い時間が必要となる。でもこれができるとひとが本当に育つと思うし、教育の理想像なのだが。
僕は何かと何かが合わさることによって、見方が変わっていくことばかりを追っていきたい。見方が変わるということが何かがわかるということであって、何かがわかるという事は見方が変わるということだと思っているんです。
読書を続けていくと、頭の中が勝手に別の(次の)展開をしてしまう。それは無限に繰り返される。当然生産性は低い。生産性など問題ではないという立場のひとや、生産性から見放されたひとが取りうる至福の世界。
私はハイパーカードが開発されたと言うニュースを読んだときに初めて了解した。そのニュースは簡単な説明しかしていなかったものの、私にはピンときた。驚くべきことに、私は他の人たちとは逆に、Macintoshに頭と手を代行させようとしていたのではなく、Macintoshを頭の中に入れようとしていたのであった。
ハイパーテキスト技術の出現はわたくしにとっても、晴天の霹靂だった。これで、従来とはまったく違う「方法」が手に入ったと思えた。しかしまだそれを駆使するという段階(環境)にはなっていないし、自分の頭の中も育っていない。あと「10年くらい」の健康寿命中に間に合うか?
我々のアタマの中で最も重視されている事は、おそらく情報操作上のコヒーレンシー(一貫性)をどのようにつけるかということである。それぞれの情報のスタックは自立していない。自立していないどころか、自分では身動きも取れない状態にいる。それが動き出すのは、電話がかかってくるときである。電話がどこからかかるかはわからない。感覚器官が送りこんでくる刺激も、ちょっとしたおもいつき刺激も、いずれも電話のベルにあたっている。
「電話のベル」はいつ鳴るかわからない。都合の良いときに鳴るかもしれないし、そうでないときも。また、鳴ったことがわかってもその内容を理解する前に忘れてしまうこともある。感覚をとぎすましておけば良いというわけでもない。すべて運命。
本当は、誰もが自分の中に、いくつもの自分と言うものを持っている。かつてプロ野球選手に憧れた自分、ピーター・パンのように空を飛べると思っていた自分、ファイティング原田のように三分間の戦いに挑もうとする自分というようにですね。にもかかわらず、社会のなかでは、たったひとつの自分と言うものに、どんどん限定されていってしまう。
これは悲しい事実だが、克服はできそうだ。特に年を取ってくると。
本を読んで解釈すると言うのは、単に一冊の本や一人の著者を相手にしているわけではない、歴史の中を循環し続けてきた多重多層のテキストを、今また一冊の本を通して読み替えするつもりでやるんだ、読書と言うのはそういうものなんだというふうに、どこかで自覚してやり続けてきたんだろうと思うんです。
確かにそうなのだろうという推測は可能だ。でもわたくしの百倍(千倍?)くらい本を読んでいる著者の言葉は重い。空海の求聞持法を思い出す。
おそらく本音を言えば、1回書いたことがうまくいってないから、また次を書くと言うふうにしてるんじゃないかと思いますよ。本当は1回書いたものにもっともっと手を入れ続けたいんだけれども、出版社が許してくれないので、次から次へと先に行くしかない。
これは、アマチュアの方が有利。体力の許す限り何百回でも読み、何百回でも書き直すことが可能。逆にそれが足かせ。
「僕は天才ではないし、天才肌と言うのとも違うけれども、1つだけ自慢できる事は好奇心。多分好奇心の天才なんだろうと思う」(中略)「世界の方が面白すぎた?」
2番めは対談の企画側の発言か。至言だが……企画側が言うのは気の毒かもしれません。
松岡正剛の本の読みかたは自分のそれに似ている。なんだか自己満足をさせてくれる、夢を見るような楽しい本でした。
(2)現在の私の棚主ページです
SOLIDA
RIVE GAUCHE
***
また来週。
すでに登録済みの方は こちら