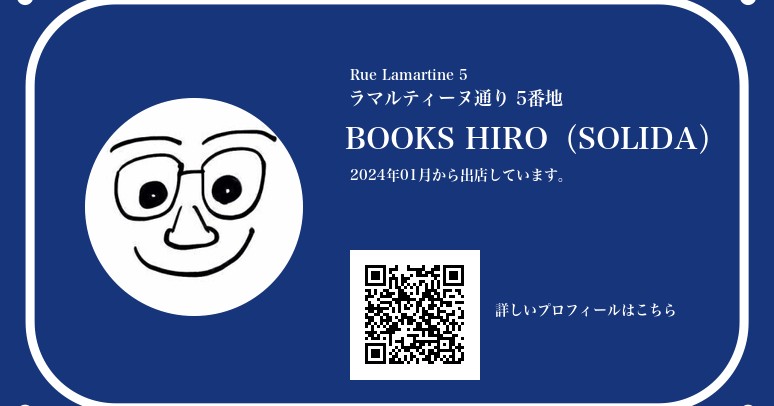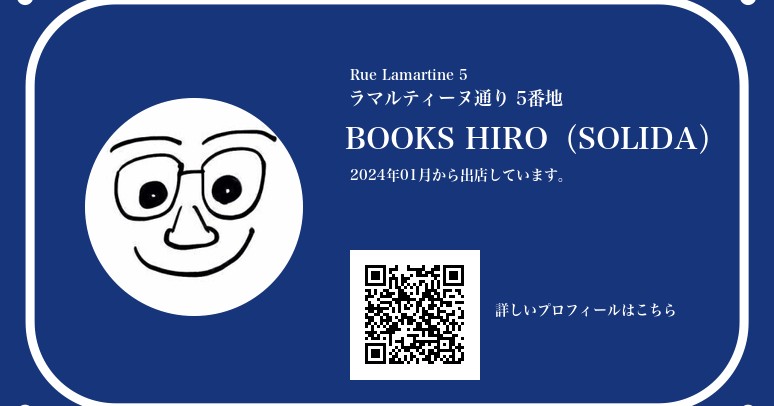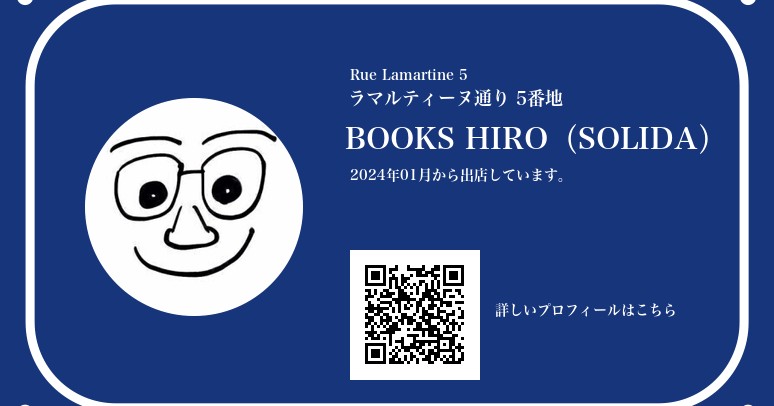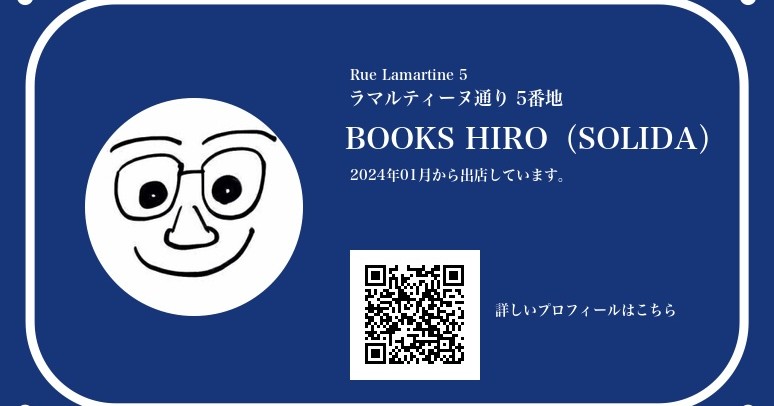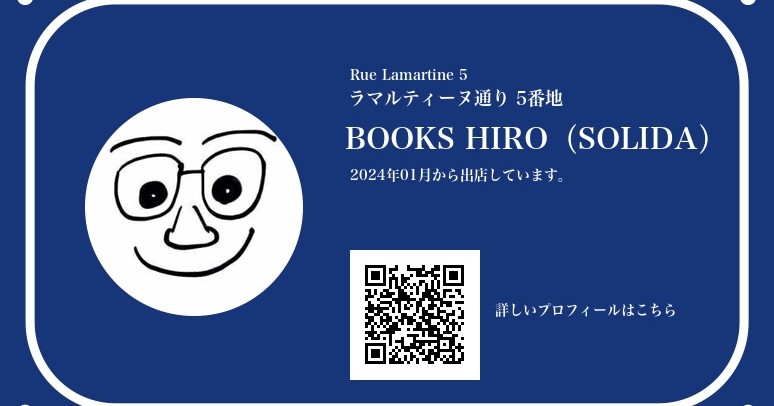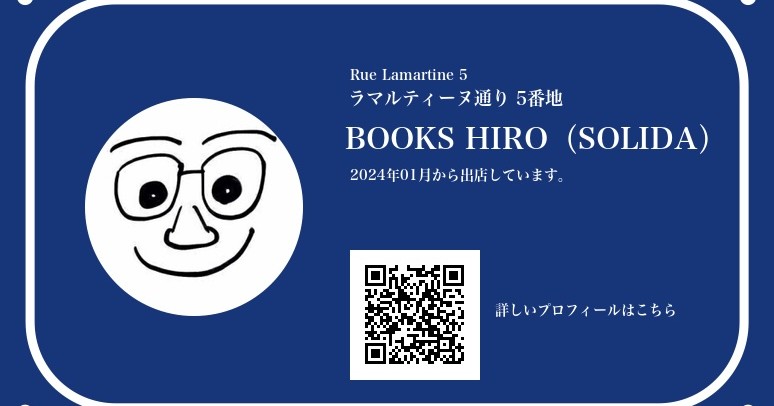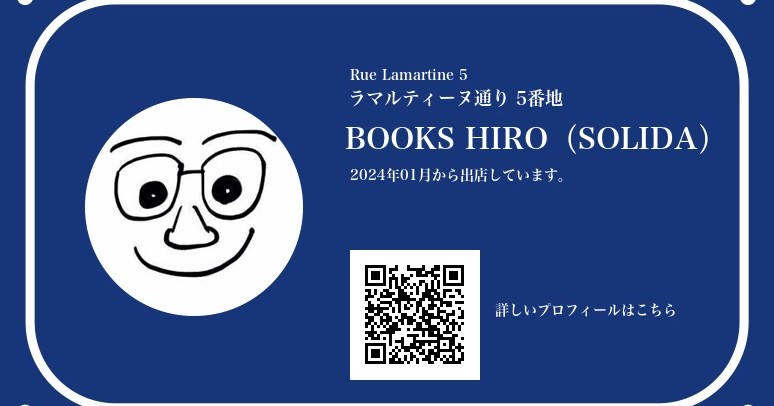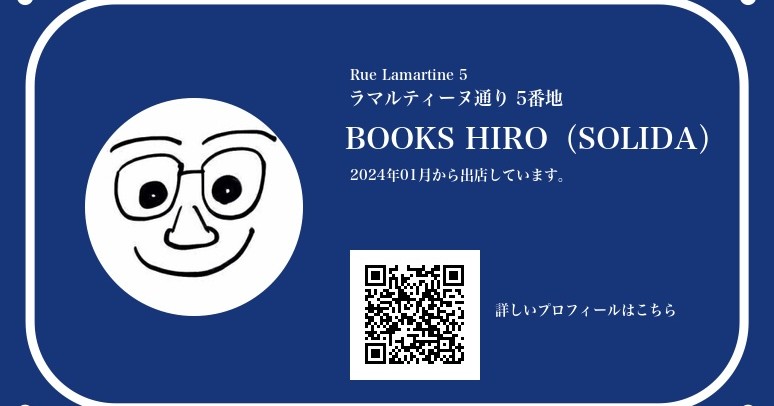BOOKS HIRO通信 第162号
(1)みなさまこんにちは
『私の本棚』(新潮文庫 2013年)をPASSAGEで一日店長のこころば書房さんより購入してすぐ読みました。鹿島茂さんを含む多くの有名な方々がご自分の本棚を維持する喜びと苦労を紹介する記事を集めたとても面白い本です。そのなかで異色なのが「本棚が、いらなくなる日」という都築響一さんの文章。引用してみます。
「……ほんとうに必要なものならば、かならず探し出せる」ということだ。自分の手元に、いつ読むのかわからないまま、何百、何千冊という本を置いておくよりも、ネットにつながったノートパソコンがあればいい。一生かかっても追いつかないほど、行きたい場所がたくさんあって、会いたいひとがたくさんいて、作りたい本がたくさんある。そういう自分にとって、いちばん必要なのは資料の山じゃなくて、いつでもどこへでも、いま住んでいる場所を捨てて移動できるフットワークだ。
たしかに、読みたい本のすべてを所蔵するのには無理があります。そしてなにより本を「読む」楽しみを味わうのが何より大切で、その本が「自分の書棚」にあるかどうかは大きな問題ではないのです。本を読んでいるうちに関連した他の本が読みたくなり、それを入手して読んでいるうちに、もっと読みたくなる。このいもづる式の読み方をしていると、小さな自分の棚にはとても収まりきらないほど、本が増殖してしまいます。ここで考えるべきなのは本を「所蔵する」という概念を拡大することです。
ところで、『堀辰雄全集 別巻2』(筑摩書房)のなかに、「蔵書目録」があります。最晩年に念願の書庫を建てた堀辰雄の愛蔵の本の目録です。病床から動けない堀辰雄が、多恵子夫人の助けを借りて自分の思い通りに本棚へ配置したようで、その分類と配置を指示するカードの写真やもちろん本棚の写真も残されています。(私は『新潮日本文学アルバム 堀辰雄』でみました。目録やカードを見るだけで楽しめます。)堀辰雄は、ほぼすべての本の題名や内容が頭にはいっていて、その時々に必要な本の題名や書架上の位置を多恵子夫人に伝えて、取り出してもらっていたようです。たくさんの本があるのですが、考えると驚くべき記憶力。
世界中のすべての書棚の本に関して、このようなことが自分にもできるのではないかと夢見るのは楽しいことでした。最近ではそれが「夢」でなく現実になっています。PASSAGEのような数多くの棚主の書棚の集合体はその有力な手段です。PASSAGEのそれぞれの棚の背後には棚主さんたちの大きな書棚がかくれているのでなおさらです。もっと考えると、インターネットで多くの書店、図書館の本にアクセスができ、入手でき、ネット上で読むことさえもできるという世界史上稀有な良い時代に読書家は居合わせていることに気づくのです。これは素晴らしいことです。
読書家の楽しみは純粋に読みたい本たちを読むことですが、それが誰にもできるという良い時代はすでにはじまっています。毎日の読書が楽しみですね。
(2)現在の私の棚主ページです
SOLIDA
RIVE GAUCHE
***
また来週。
すでに登録済みの方は こちら