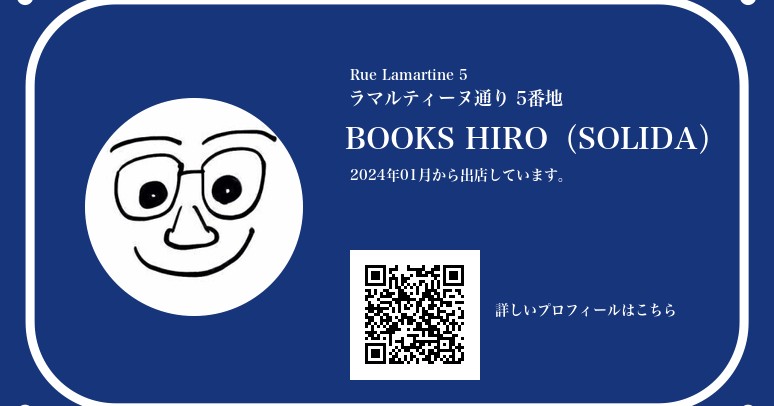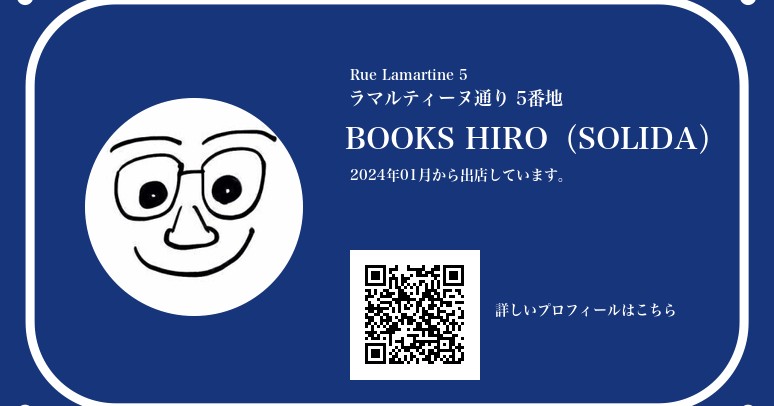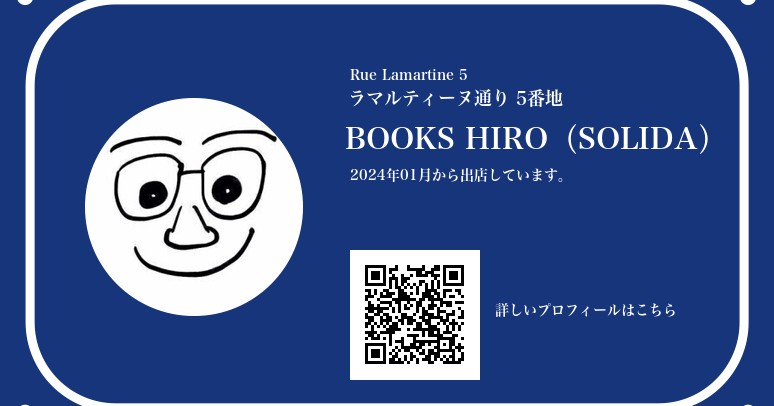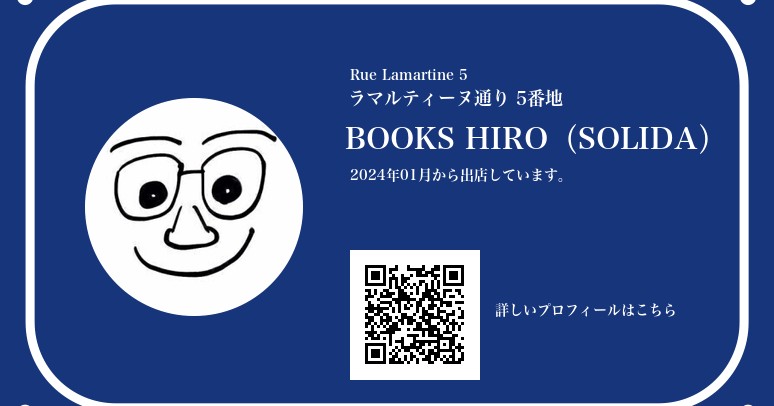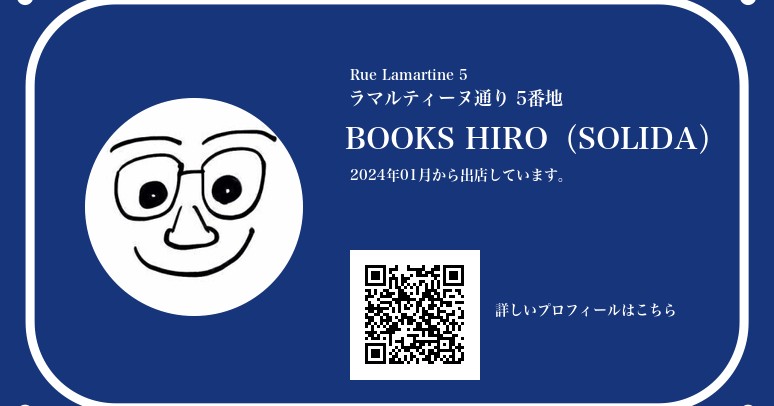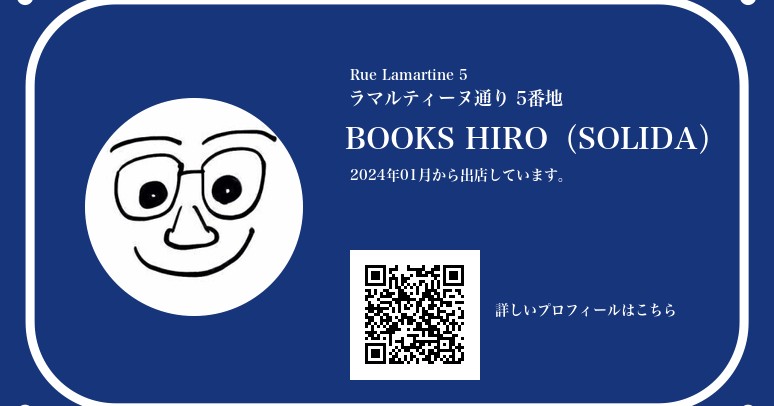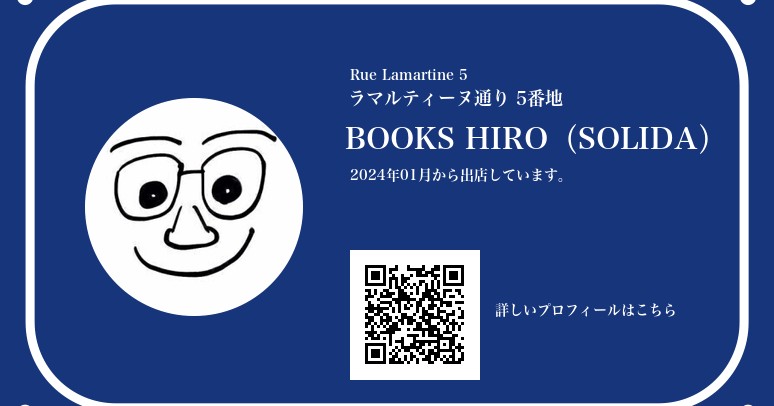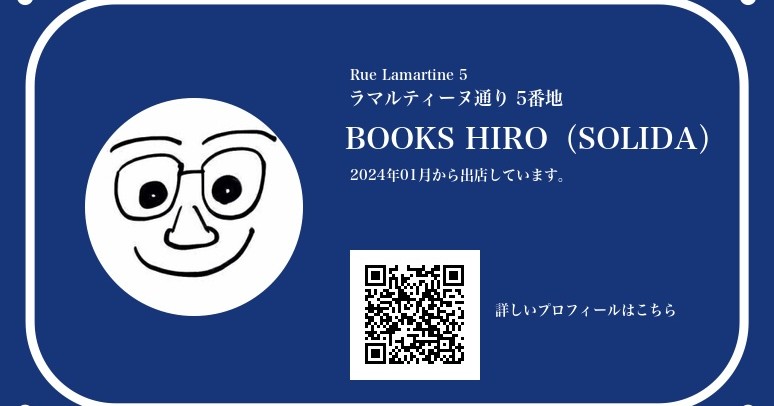BOOKS HIRO通信 第173号
(1)みなさまこんにちは
PASSAGEで「あかつき」さんが一日店長をなさった日、そのフェア台から『本の雑誌 2025年2月 500号記念号』を購入した。500号とはよく続いたものだ。創刊の1976年から時々読んでいた。最近はご無沙汰していたが、なつかしい過去の記録満載の500号を読めたのは「あかつき」さんのおかげだ。
86ページからの津野海太郎氏の書いた辛口の回想記事が目についた。主旨は、電子本の「未来」を矮小化したKindle本は新自由主義・拝金主義の産物で、Kindleが普及してからは失望して電子本に関わるのを控えたとのこと。現在に警鐘を鳴らす意味で書かれた少し過激な意見とも思える。津野海太郎氏の言うような、個人が自由に作れる豊富な機能を持った「電子本」は必要だし、現在の環境なら、個人で作ることも可能だという気もする。
そこで萩野正昭氏の『電子書籍2020 本の存り方は変化する』(*)をVOYAGER(理想書店)で「買って」、電子書籍なので即読みした。(Kindle版もあるがビデオへのリンクが埋め込まれていない。つまり「矮小化」されたもの。)
この本自体は津野海太郎氏のおっしゃるような多機能の「電子本」になっている。この本に書かれていることを私なりに解釈してみた。
1.『電子書籍2020 本の存り方は変化する』でいう電子本の構成の特徴は「シンプル」であること。
テキストと写真が主で、写真は独立したページに配置される。こうするとページへの文章の配分に気を使う必要がない。あとは映像や音など関連情報へのリンクのみ。付随して音声読み上げ機能や翻訳機能、読者のフィードバック機能なども持つ。
2.今のいわゆる「電子書籍」は、すでに紙の本として出版されたものを便利に読むものとしか考えられていないが、実は電子書籍はもっと広い機能を持つものと捉えることができる。
3.現在のテクノロジーがあれば、このようなシンプルながら広い機能を持つ電子書籍を個人が容易に作る事ができる。もちろん、この電子書籍を売って利益を得ようとすれば、個人が経営努力をする必要がある。それができない人は、商業資本の助けを借りることになる。
4.利益を度外視することができれば、今までより遥かに多くの個人が自分の好みに応じて自由に電子書籍を作り、自由に読者に読んでもらえる。出版で儲けるという考え方を捨てることができる個人は、著作権を守りさえすれば、読み書き自由で多機能な電子書籍の世界に住むことができる。
なるほど、私のような金から自由な遊行期老人(幸いにして金儲けを超越した老人)が書くことは、今すぐにできる。精神衛生上も良い。明日といわず今日からはじめたい。今までに書き溜めたブログやnoteやニュースレターを考えると、実はすでにはじめているとも言える。一方、読むことを考えると、青空文庫や国会図書館デジタルやInternet Archiveは今でも無料で読める。これらをブラウザで読みやすいように編集したリンク集を作っておけば良い。
ところでいま、辻邦生の電子版全集の2回目配本の『春の戴冠』を読んでいる。これはKindle本だがかなり頑張っている。津野海太郎氏のいう理想の電子本にほんの少しずつ近づいていると言える。きっと未来は明るい。
(2)現在のBOOKS HIROの棚主ページです
SOLIDA
RIVE GAUCHE
***
また来週。
すでに登録済みの方は こちら