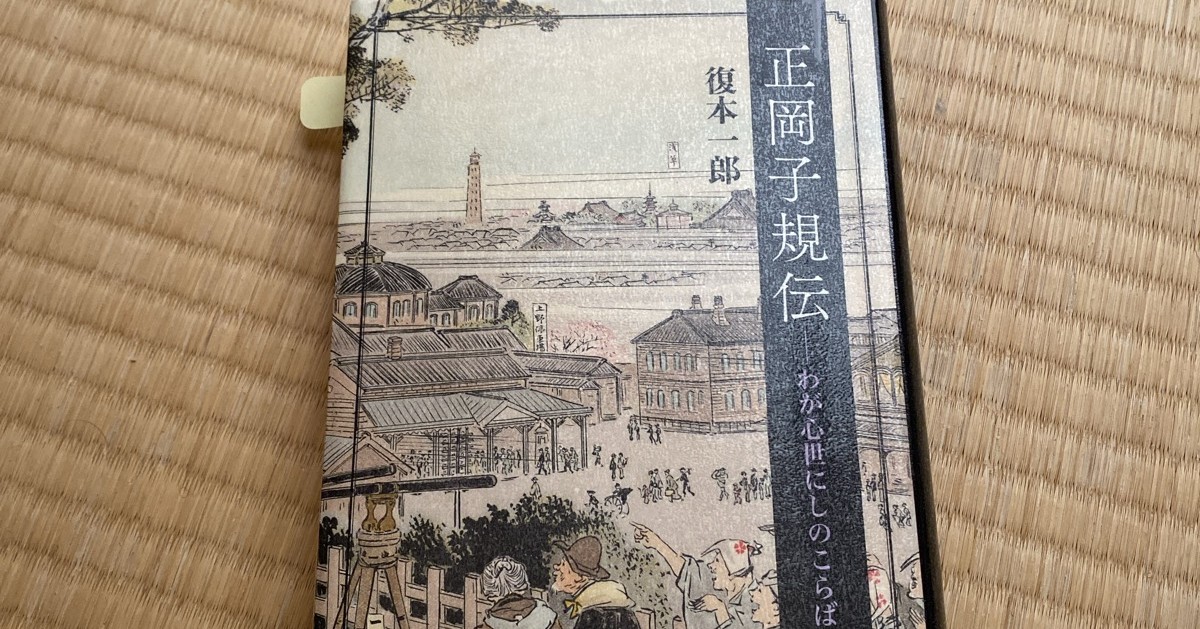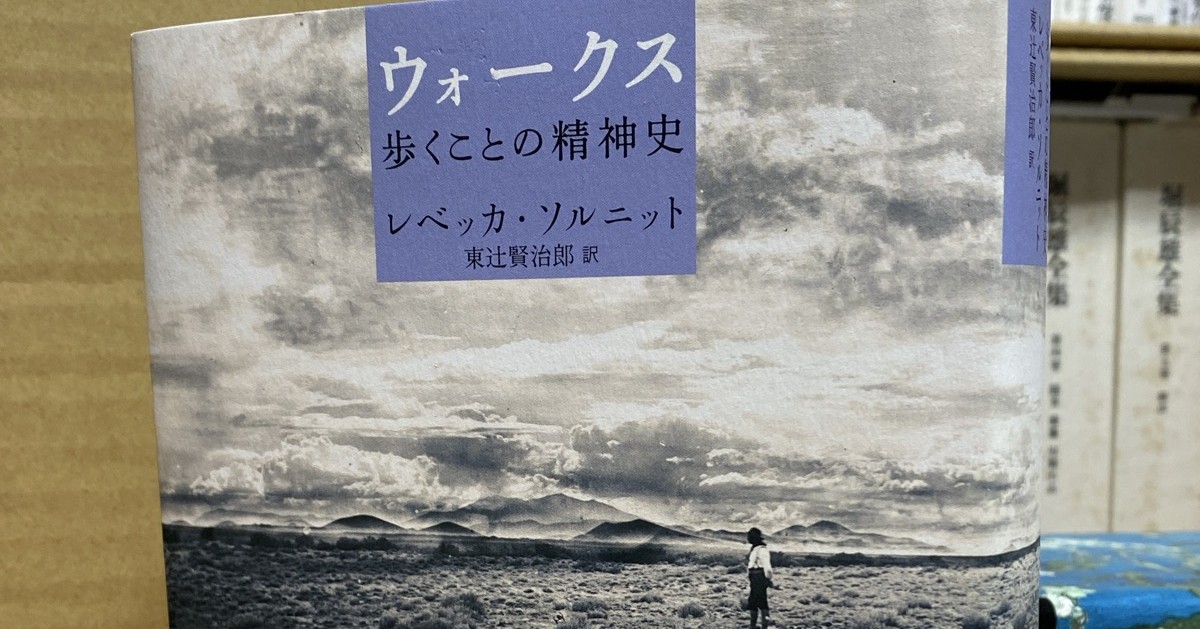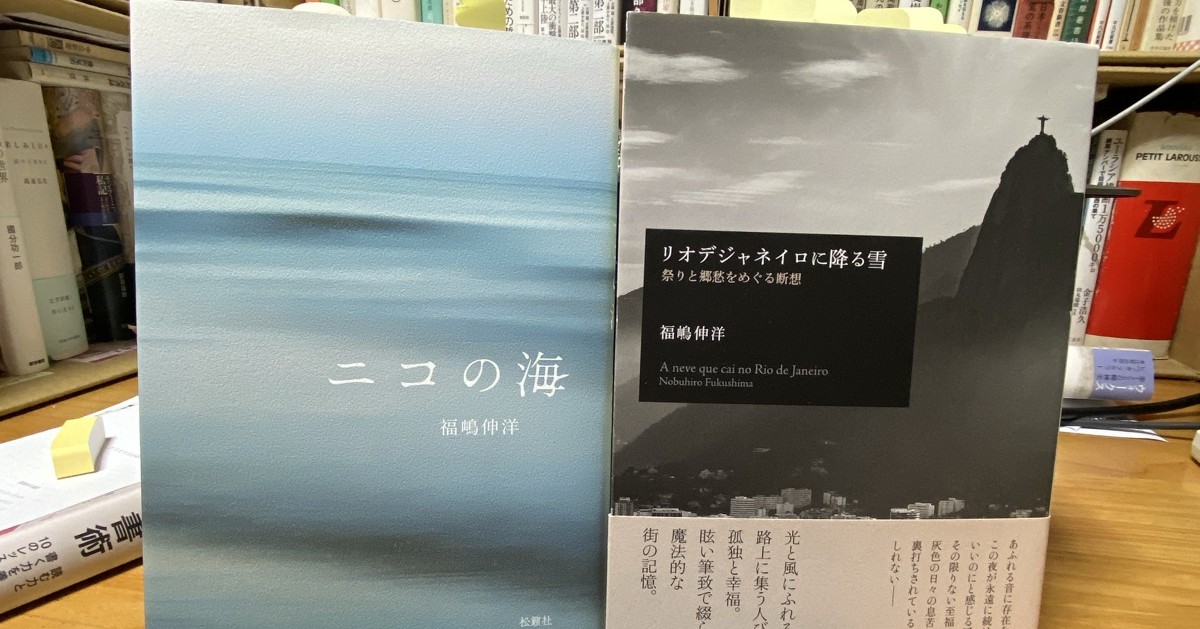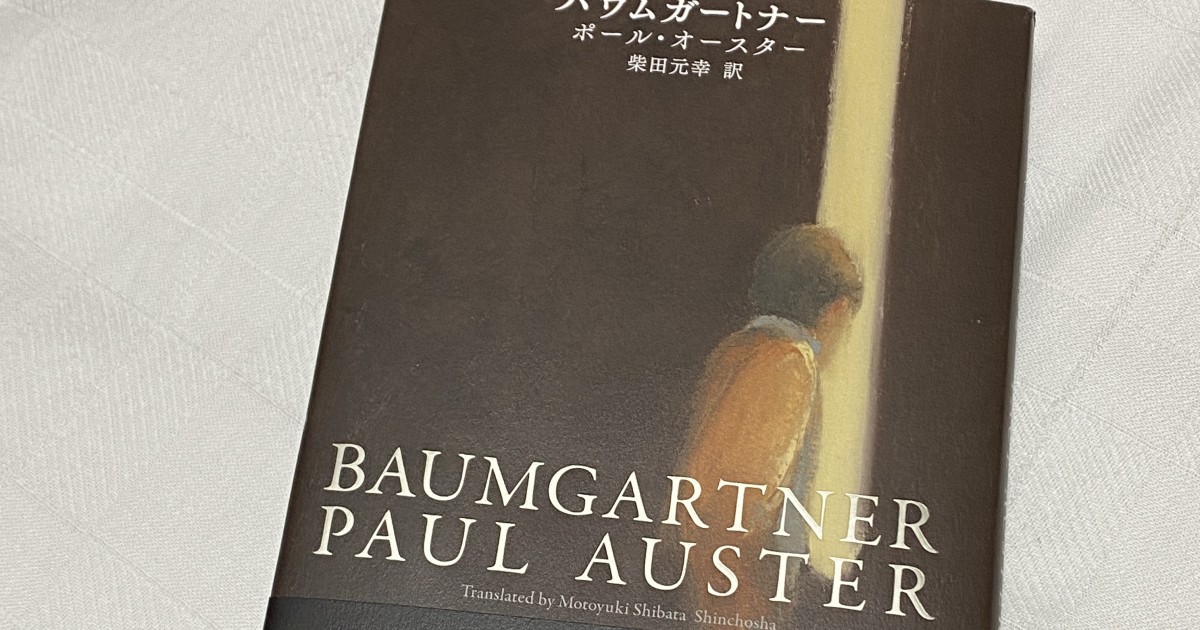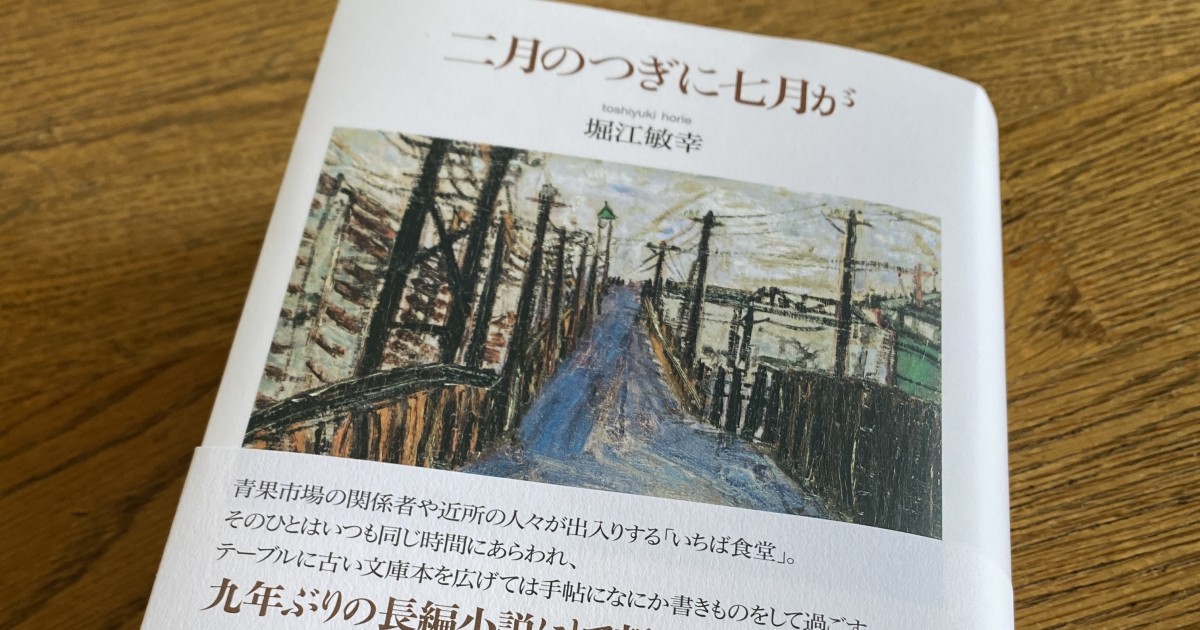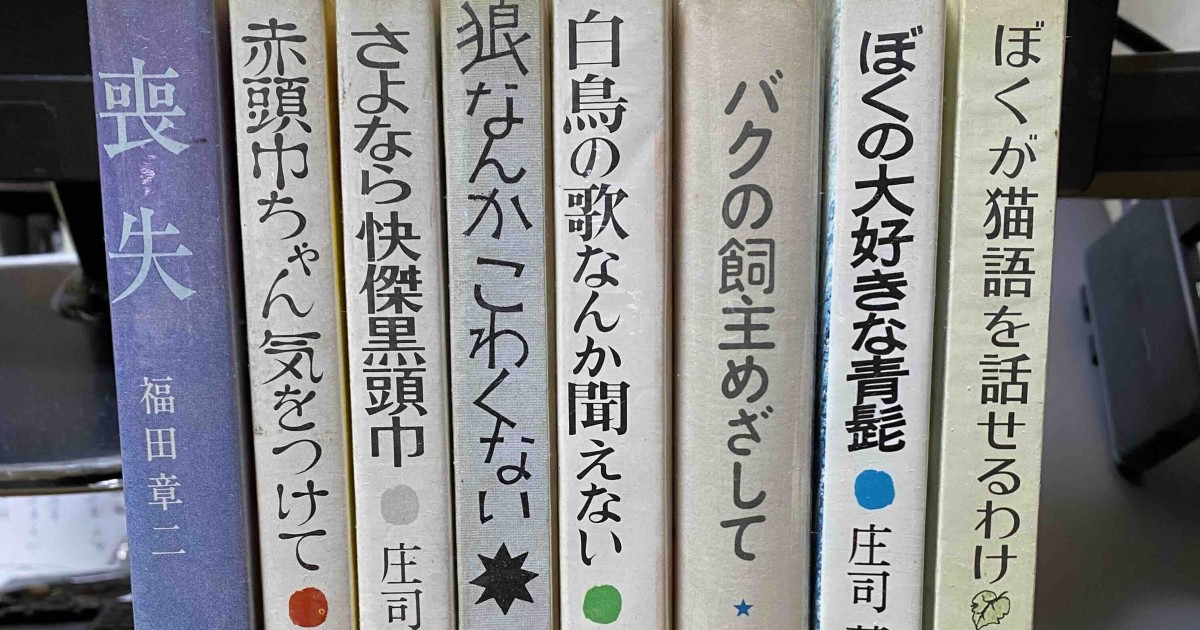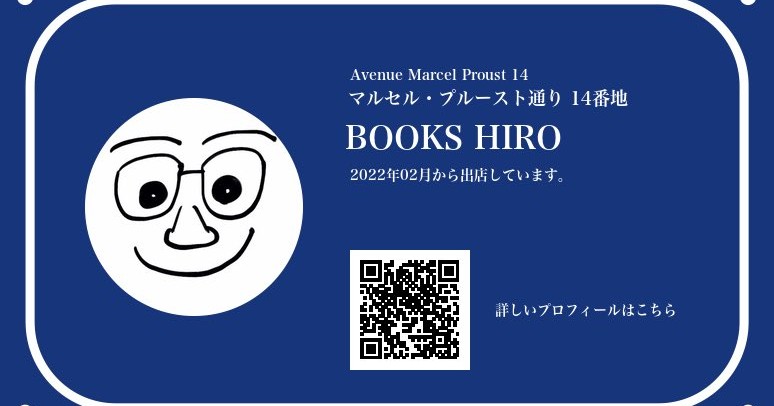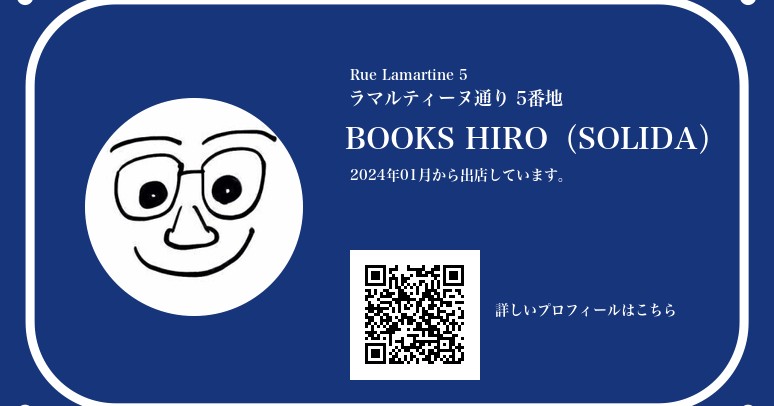BOOKS HIRO通信 第129号
(1)みなさまこんばんは
今年もよろしくおねがいします。
佐藤亜紀さんの「歴史小説の技法」講座の予習として、以下の二冊の本をこの三ヶ日で読みました。予習と言うよりは自分のような単なるディレッタントが受講して意味があるだろうかという疑問の解消に役立つだろうというつもりです。これらの本は早稲田大学、明治大学での講義の内容をまとめたものとのことです。
一冊目の『小説のストラテジー』(2006年 青土社)で、印象に残ったところを引用してみます。
「一方的な送り手である表現者と、一方的な受け手である鑑賞者と言う関係からは、いかなる対話も生まれてきません。」(23ページ)
「あらゆる表現は鑑賞者に対する挑戦です。」(25ページ)
「かつてウラジーミル・ナボコフは「二度読む読者こそ良い読者である」と言いましたが、それは、作品の諸要素やその相互の関係を把握した上で、読まなければ良い読解はできない、と言う意味です。」(40ページ)
「個人的には、物語に傾斜した作品は、記述に傾斜した作品に比べると、圧倒的に不利と言う気がしますが、要は、それがどれだけ豊かな享受の体験を提供するか、であって、後は読み手の技量に委ねられる問題だと言えないこともありません。」(75ページ)
「作家自身でさえ、書き上げた作品には一読者としてしか接することができません。書いている最中に何が起こったのかを見て取ることができるのは、作品を通してだけです。」(85ページ)
同じく二冊目『小説のタクティクス』(2014年 筑摩書房)。
「……ひとつ、前提があります——書き手と読み手が同じ世界に住んでおり、書き手が見たものと、読み手が書かれた言葉を読み取って、思い浮かべるものが一致していることです。さもなければ果たして書き手がそれをきちんと書いたかどうか、読み手には判断できません。同一の世界に住んでいればこそ、言葉で何かが指し示されたとき、指し示された対象が、お互いにとって同一であること——単に同一のものであるだけではなく、その様態においても、同一であることに、疑念の余地はなく、より正確で、適切な言葉がそこに現れ、より適切にその様態を指し、従来指示に使われていた言葉以上に実態に即した姿が現れたことが認識できる訳です。」(136ページ)
これらを読んでみて、今回の「歴史小説技法講座」を「書く人」としてでなく、「読む人」として参加することに、自信がもてたかというと、そうでもありません。相変わらず「不安」ではあります。でも講座を受けてみたい気持ちには変わりはないとは言えます。
鑑賞者の立場は単なる受動的なものだけではないとわかったからです。
さて、講座の一回目は1月25日なので、来週中には決断が必要です。もう少し悩みます。実はこの段階が楽しいのですが。
(2)現在の私の棚主ページです
SOLIDA
RIVE GAUCHE
明日以降の予定。4日と6日と10日はSOLIDA勤務、あと7日と9日はRIVE GAUCHEで勤務です。
すでに登録済みの方は こちら