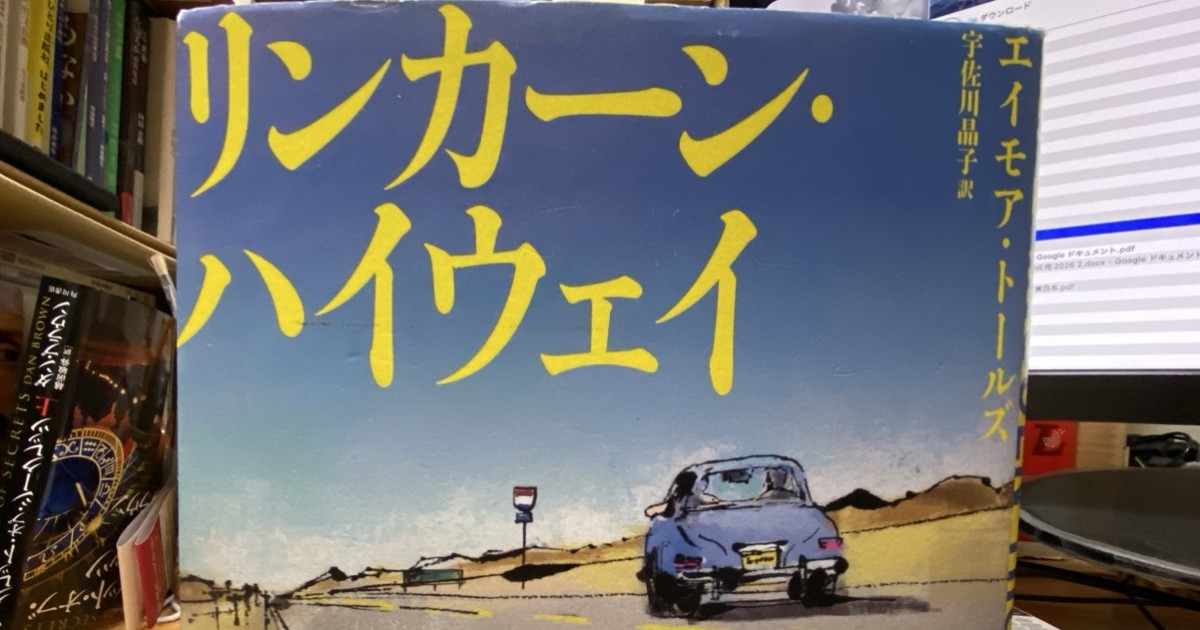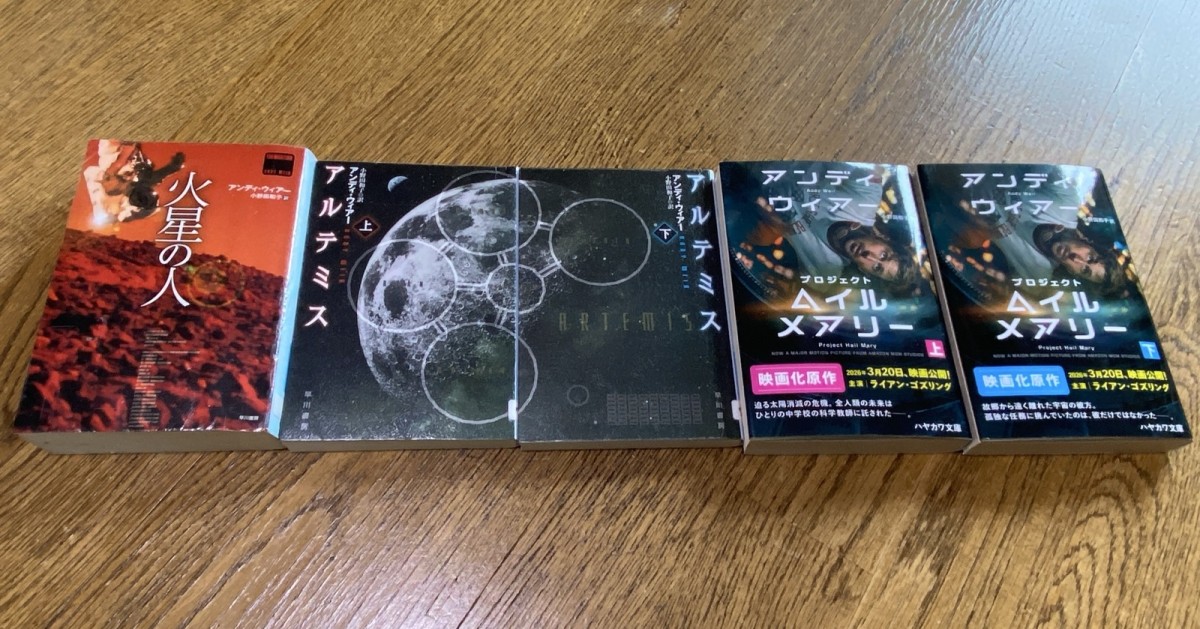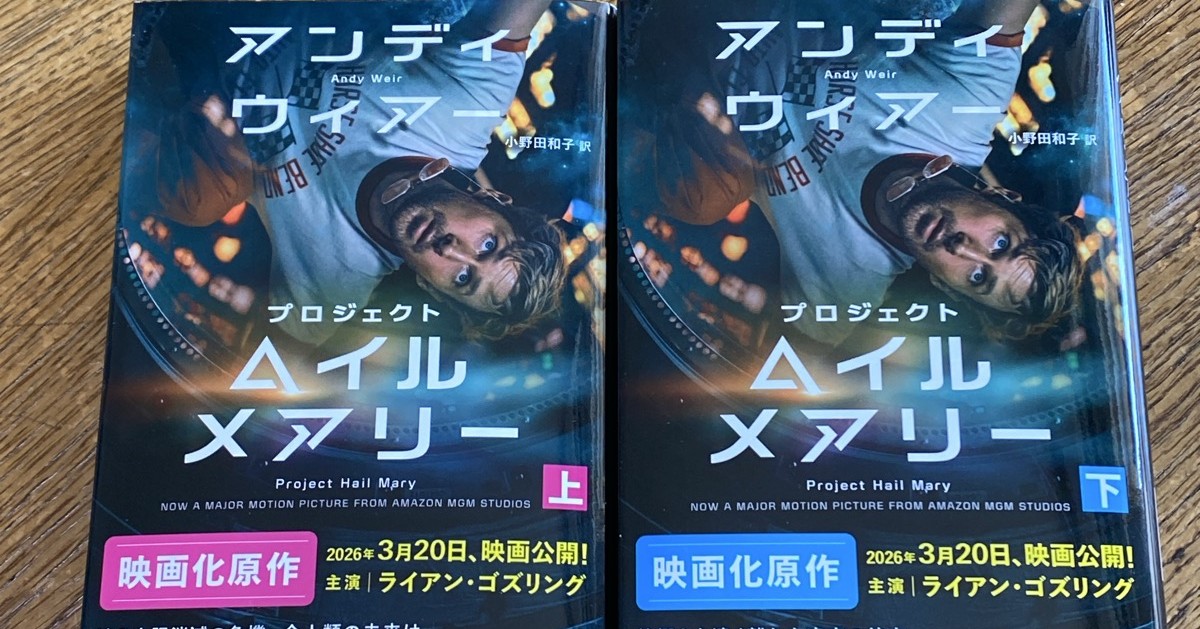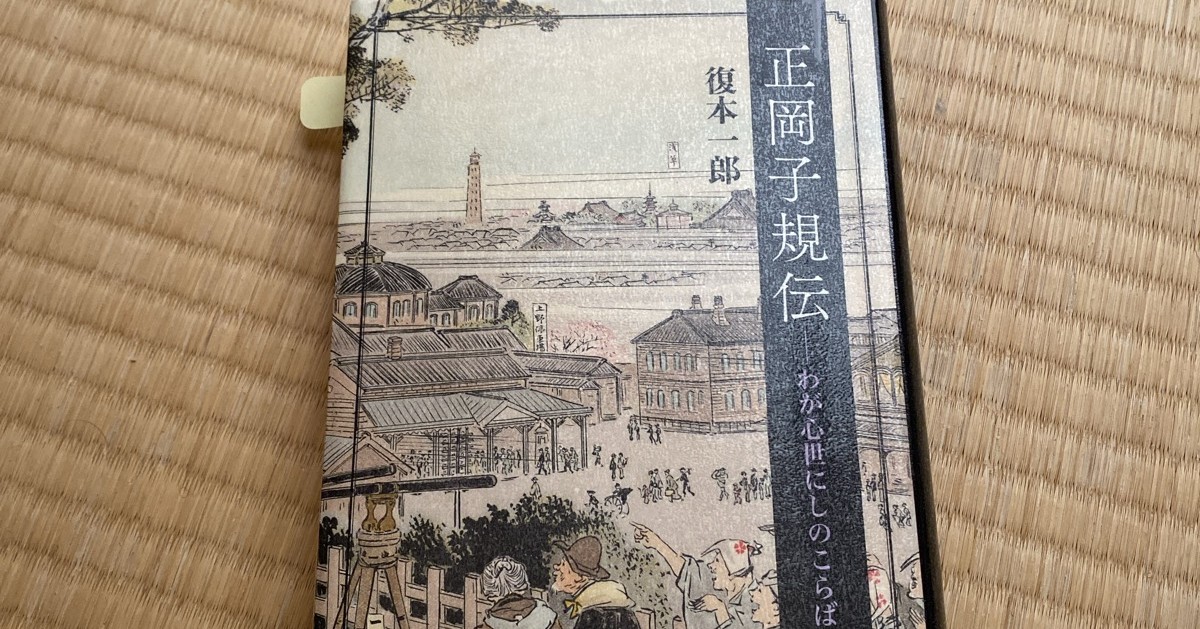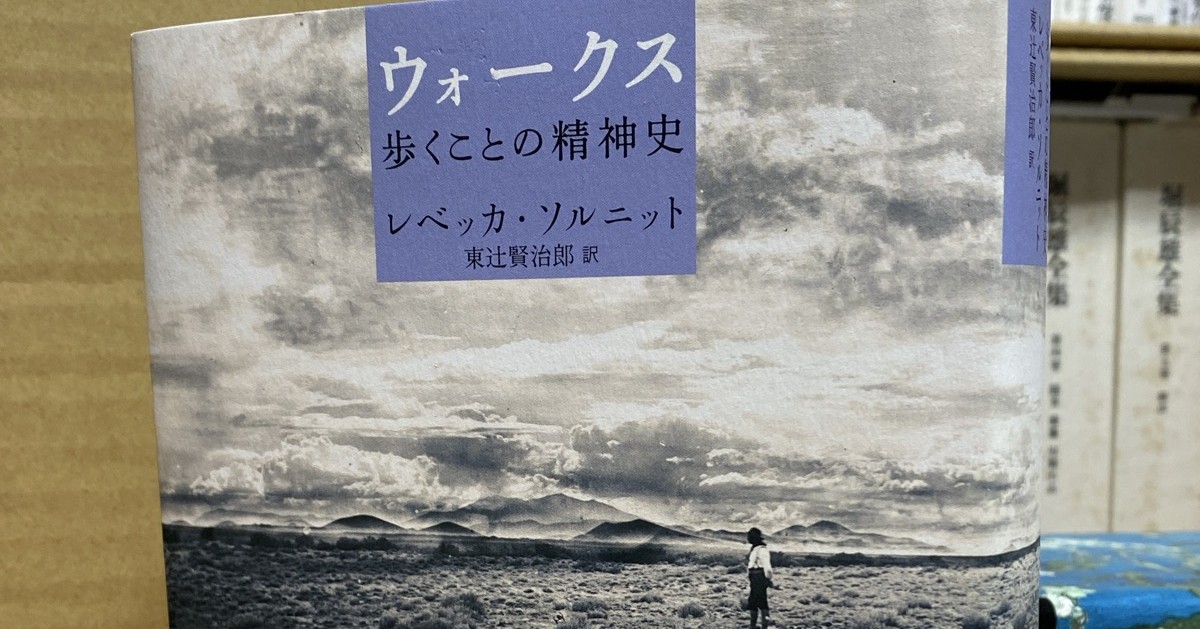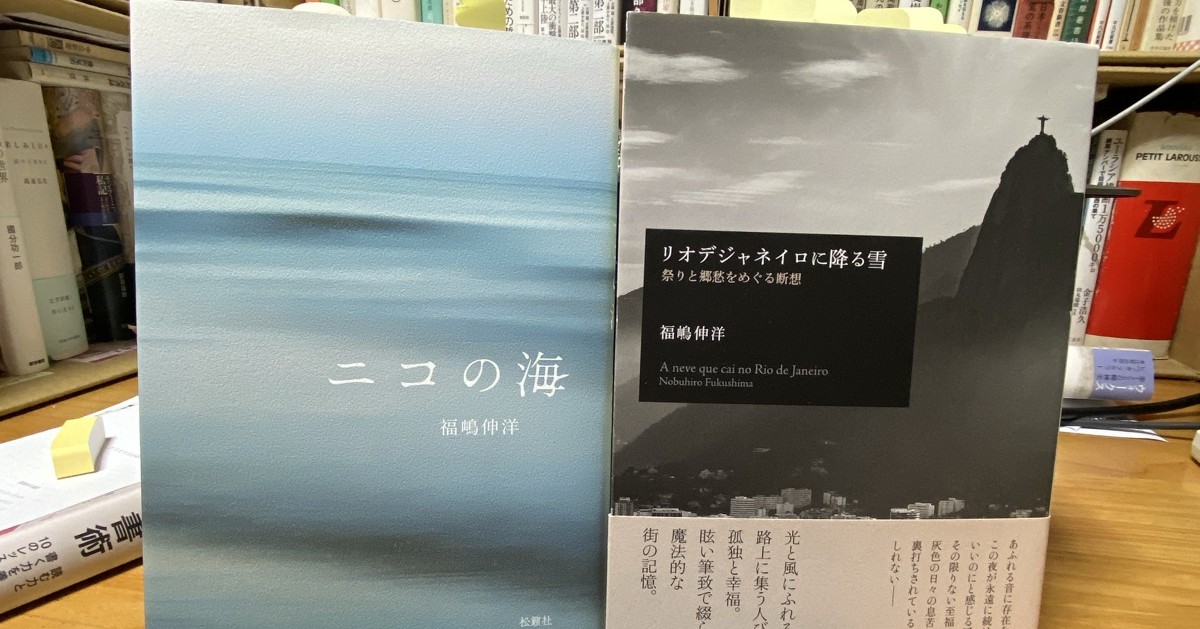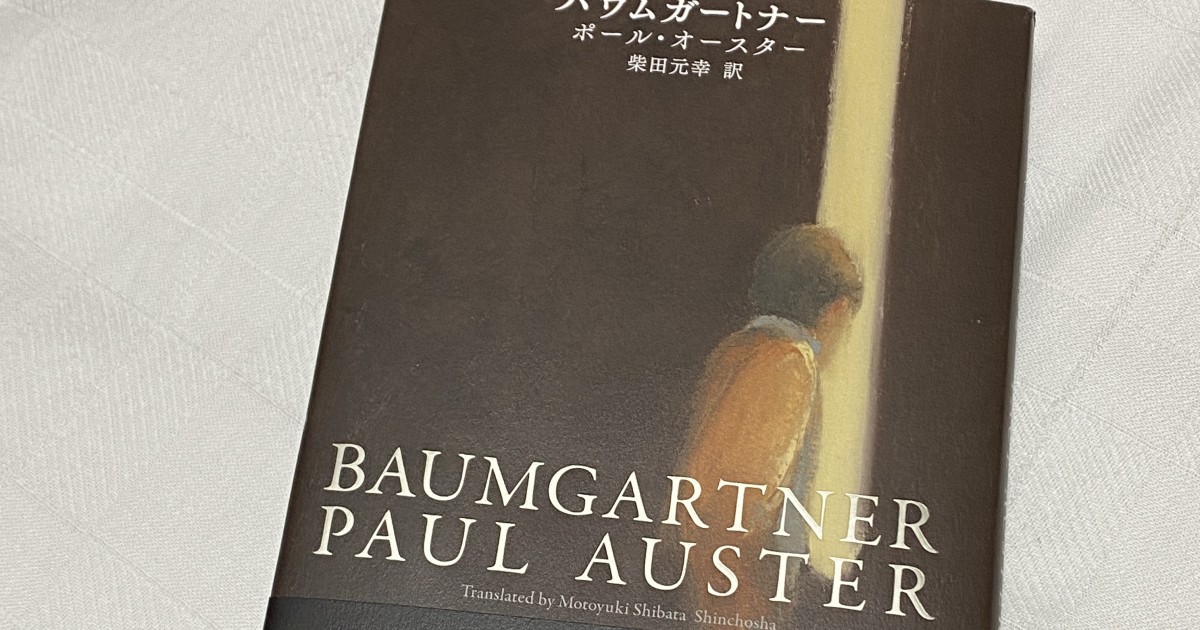BOOKS HIRO通信 第104号
(1)みなさまこんばんは
先日逝去された小田光雄氏の著作をいくつか読みました。『古本屋散策』、『図書館逍遥』、『ヨーロッパ 本と書店の物語』、『書店の近代』の4冊です。『古本屋散策』は第29回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を鹿島茂さんの選考により受賞しており、2019年に上梓されたときすぐに読みました。
(鹿島茂さんによる『古本屋散策』の書評はこちらです。 https://allreviews.jp/review/3784 )
他の3冊も今回初めて手に取りましたが、どれからも深い感銘を受けました。小田氏は出版・取次、書店・図書館に関する資料を調べ、そして何より膨大な数の書籍に当たり、日本の近代以降現在に至る状況をの丹念な調査を終生続けられました。その研究の深さと広さには圧倒されるばかりです。
特に印象に残ったのは、『図書館逍遥』のあとがきにある一節です。「どんな図書館にも、市民やユーザーや貸出し冊数といった背後に、多様な読者と本と読書をめぐる物語が潜んでいるにちがいない。」この言葉は、書物を介した人々のつながりの豊かさを示唆しています。単なる統計や数字ではなく、そこに潜む人間模様や物語の存在を見出す小田氏の視点は、私たち書籍に関わる者にとって非常に示唆に富んでいます。そして、これは図書館にかぎらず、『ヨーロッパ 本と書店の物語』『書店の近代』を読むと、出版社・取次店・書店においても、良い本を作り・流通させ・読者へ届ける営みは企業の利益とは別の視点から考える必要があることを示しています。
現在構想している共同書店の棚主同士のコミュニティ構築、この取り組みにおいて、小田氏の残された仕事は大きな指針となるでしょう。書籍を通じた人と人とのつながりという視点は、この活動にも新たな深みをもたらすに違いありません。
例えば、棚主それぞれが選ぶ本には、その人の人生経験や価値観が反映されています。そこには小田氏の言う「物語」が潜んでいるのです。棚主同士が交流を深めることで、単に本の情報を交換するだけでなく、お互いの「物語」を共有し、理解を深めることができるでしょう。
さらに、棚主コミュニティが成長していけば、そこにはまた新たな「物語」が生まれていくはずです。小田氏の研究は、過去から現在に至る書籍文化の歴史を紐解くものでしたが、私たちはその延長線上に、未来の「物語」を紡いでいく責任があるのではないでしょうか。より豊かな棚主コミュニティの構築に向けて、棚主さんたちと一緒に一歩ずつ前進していきたいと思います。
(2)現在の私の棚主ページです
来週の私のバイトスタッフ勤務は日曜日、月曜日です。
すでに登録済みの方は こちら