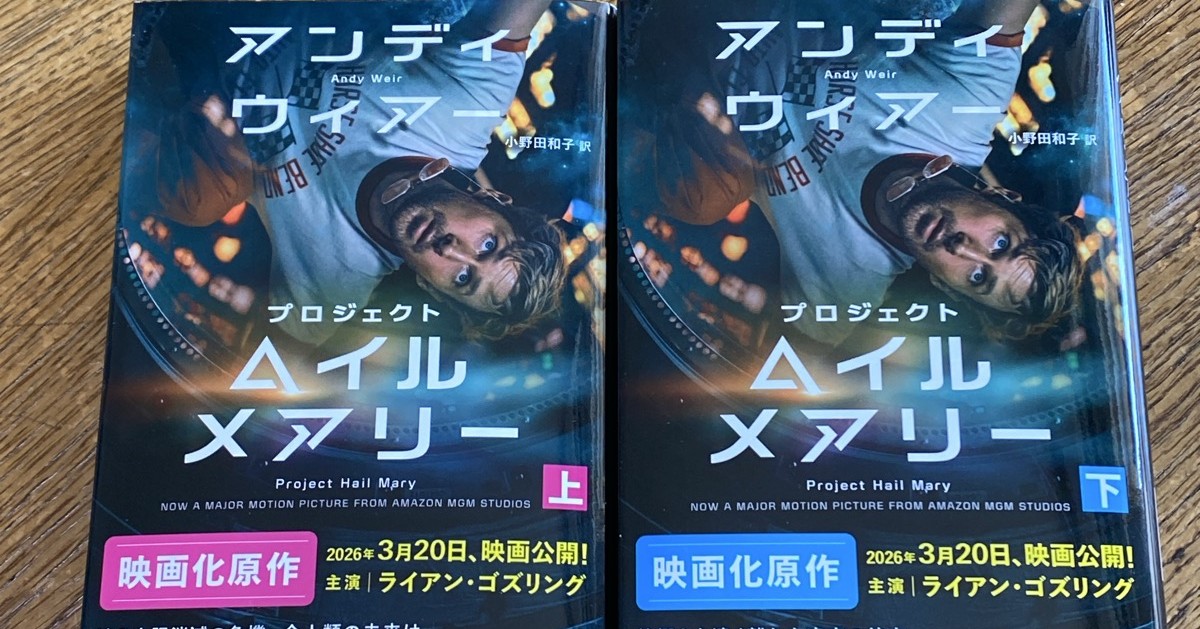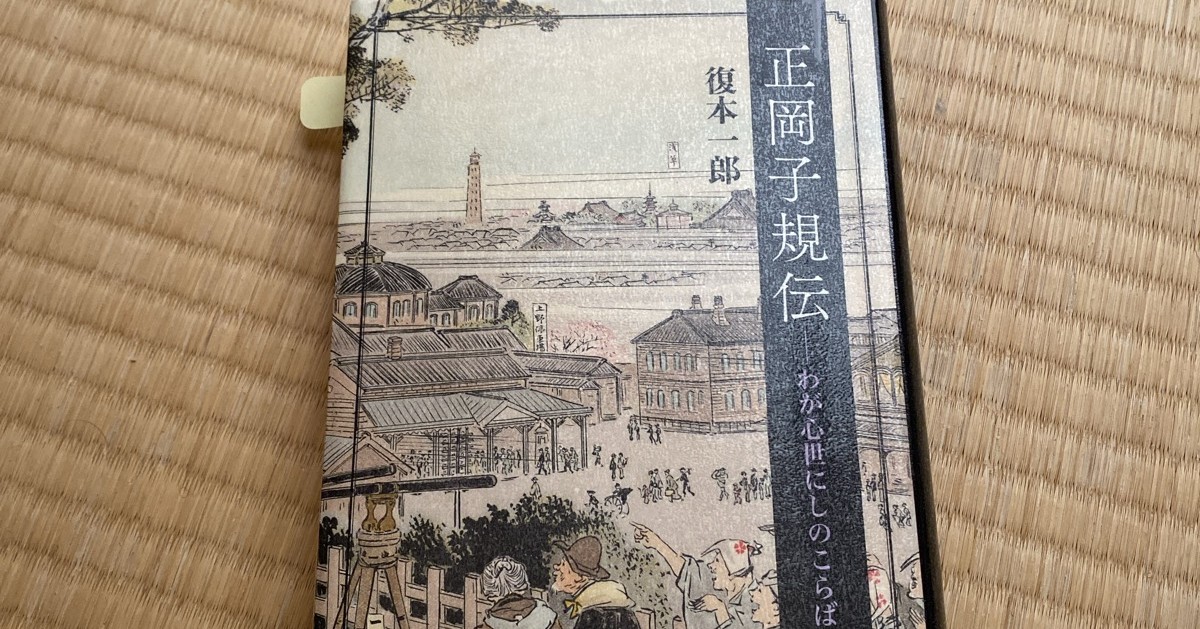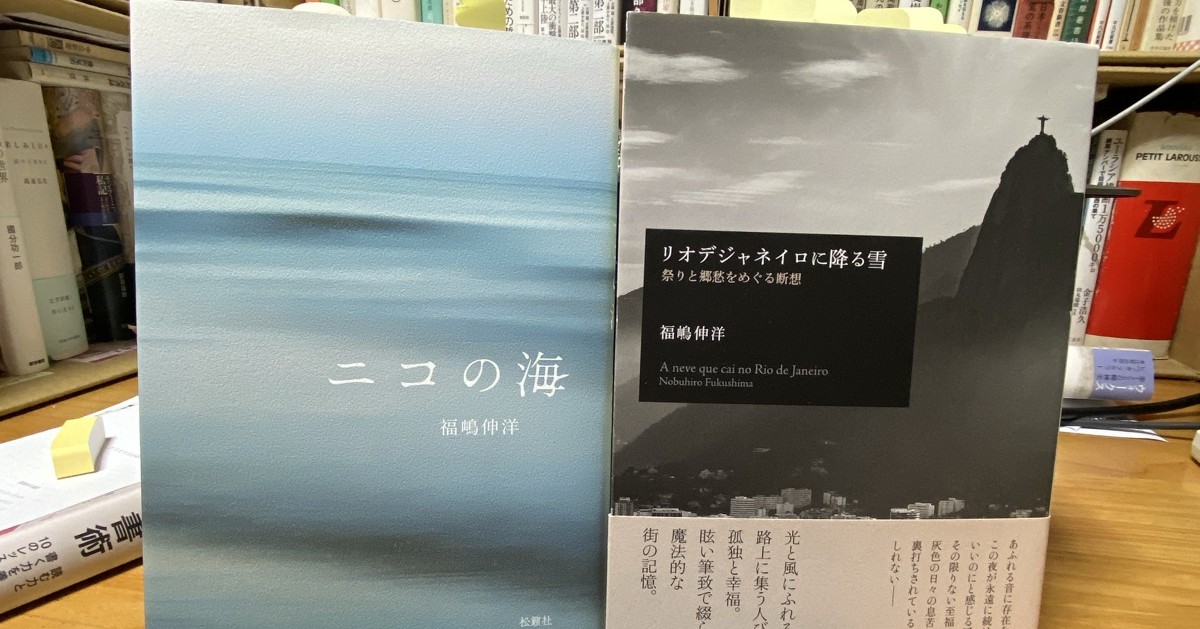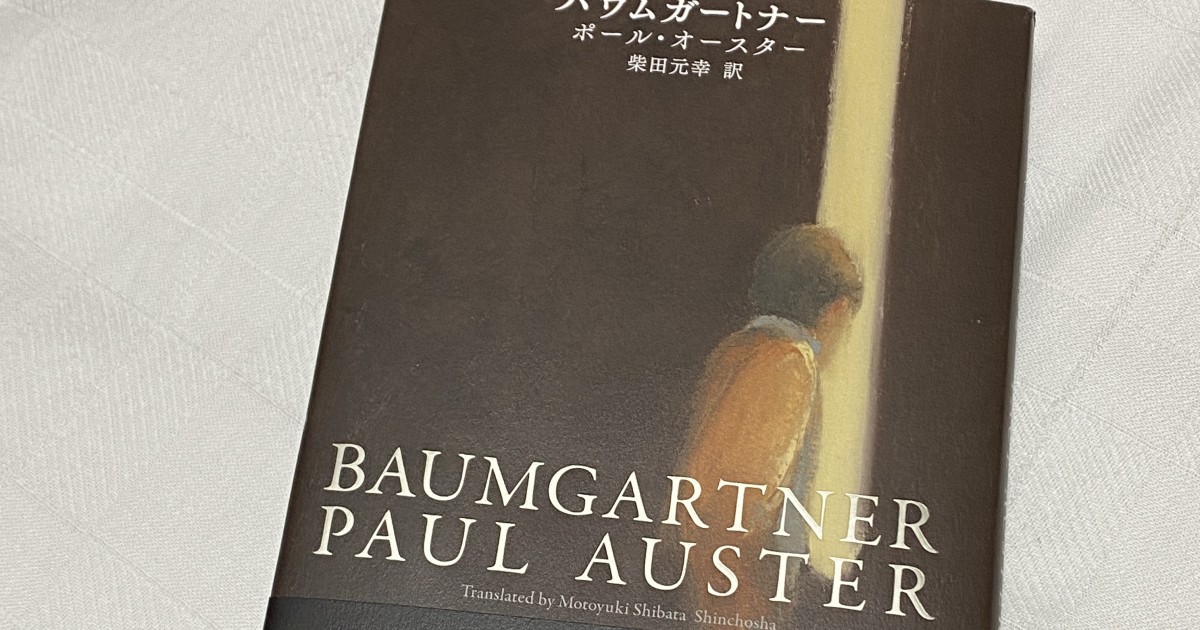BOOKS HIRO通信 第178号
(1)みなさまこんにちは
『二月のつぎに七月が』(堀江敏幸著 講談社刊)を読んだ。700ページを3日半で読んだので、熱中して読んだと言える。大部の本で、電車の中や寝転んで読んでいると、腕が痛くなってしまった。
市井の「普通の」人々の生活を細かに描写することで、登場人物をどれも「普通でない」素晴らしい存在と化けさせる堀江節満載の長編小説だ。7年にわたって『群像』に連載されたらしいが、この長編をまさに細心の注意のもとに書き続けたことに敬意を表する。人々の細かい心の動きを、会話や行動の描写で間接的に的確に表現する手腕の継続もすごい。
いつもよれよれのコートに古い文庫本とその書抜き帳を忍ばせる老人。老人がよく通うが控えめに振る舞っている食堂の従業員の女性と食堂の料理人。彼らふたりはこの控えめな老人に好意を持っている。優しく接する。
コートに忍ばせた古ぼけた文庫本は、巻末の「主要引用・参考文献」によると、『アミエルの日記』(全8冊 河野與一訳 岩波文庫 1935〜1941)らしい。老人の戦死した父親が、戦場でも大切に読んでおり、戻らなかった遺骨の代わりの遺品として老人にもたらされた。老人はこの本に父親の生きた証をみつけるべく、丹念に読み、気になったところを手帳に書き込む。難しい固有名詞などは図書館に行って百科事典や地図を調べる。読んでかつ書いているうちに、手帳は100冊を超える。徐々に老いがつのり、図書館では百科事典を持てなくなり、周囲の人の力を借りるようになる。
老人は若い頃、そろばん塾のバイト講師をやっていた。老いたいまでも、暗算は得意で、食堂の経理計算をやっている最中に電卓が故障して困った従業員と料理人を、暗算能力で驚かす。塾のオーナーを尊敬し、オーナーの娘に淡い恋心を持つが、打ち明けられずじまい。地味な経理の仕事をある会社で定年まで続けた。定年後の貧しい一人暮らしでの唯一の生きるよすがはこの文庫本を読み、書き抜きを作ること。だがなかなか父の面影は蘇ってこない。老人はいたずらに年を重ねていく。
終盤での様子を575ページから引用する。
父の遺品としての文庫本を何度も読み、理解できてもできなくても、気になる箇所をしつこく書き写しているうち、自分の文字に対する抵抗感や嫌悪感が薄れて、備忘のためならこれでもいいと思い切れるようになり、まとまった分量の文章を綴ることにある種の慣れが出てきた。地道な写経には、自分でも認識していないなにかを開いてくれる功徳があるのだろうか。
これは今の私に「刺さる」記述だ。まさに、いま、私も同じことをやっていると思える。ごく端的に面をとらえると、読むことと書くことは表裏一体、切り離せないということだ。こんな行為を一生続けていくと思う。
老人の「役に立たない」読書という行為は來世に向けて無限の重みを持つ。そろばんの最も美しいすがたは、「ご破算」後の姿という記述があるが、老人は全8冊の書き抜きを終え、人生の終わりを迎えようとするときに、みごとに読書の「ご破算」を行おうとする。
(2)現在のBOOKS HIROの棚主ページです
SOLIDA店
RIVE GAUCHE店(こちらは今年12月いっぱいで閉店します)
***
また来週。
すでに登録済みの方は こちら